|
第303回例会 細見 純子 : 7月号
今回は講演資料で共同著作権部分のものもあり、すべての資料は配布できずで、講演要旨は講演者自身が報告させていただきます。 講演内容は、バックキャストから考案し、近著である「~持続的成長を目指す羅針盤~SDQテンプレート実践テキスト」と、私が永年携わってきた品質管理との繋がりも含め、以下項目を紹介しました。 1.品質、品質管理とは何か 2.2030年の品質保証の考察 2-1)モノの品質保証 2-2)コトの品質保証 2-3)2030年以降の品質保証の仕事で大きくかわること 3.「コト」「モノ」「サービス」「ソリューション」 4.2030年以降のお客様が求める3つの品質 5.なぜSDQキューブなのか 5-1)SDQキューブとそのめざすところ 5ー2)ツールとその手順 5-3)活用事例「スマートハウス」 6.まとめ 冒頭に「品質」について、皆さん個々の定義をお尋ねして、それぞれの解釈があることを確認してから、私の定義をのべました。所属する中部品質管理協会で学び、普及してきた定義は以下です。
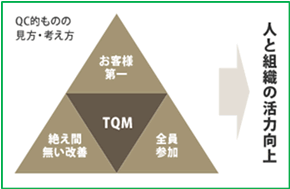 この内容を、中部地区企業は、第2次世界大戦後の日本的品質管理の中心的指導者であり、初代南極越冬隊長など八ヶ岳のように多様な専門分野で功績を遺した故西堀榮三郎博士より直接に伝授いただいた。その中核にトヨタグループがあり、同社は「品質」を同社の競争力として掲げているが「トヨタにおける全社的品質管理」の企業風土としくみにそれが確認できる。
この内容を、中部地区企業は、第2次世界大戦後の日本的品質管理の中心的指導者であり、初代南極越冬隊長など八ヶ岳のように多様な専門分野で功績を遺した故西堀榮三郎博士より直接に伝授いただいた。その中核にトヨタグループがあり、同社は「品質」を同社の競争力として掲げているが「トヨタにおける全社的品質管理」の企業風土としくみにそれが確認できる。右図参照(トヨタ自動車(株)HPから図を引用) 日本的経営品質の特徴は「全員参加」にあり、モノづくり現場だけでなく、社内のすべての仕事に携わるすべての人が品質を保証する役割を担っているとする。トヨタ自動車(株)では、マネジメントにおいて、その工程が見えにくいホワイトカラーに対し「自工程完結」という名称をあえてかかげ、2007年から具体的取組も始めた。「自工程完結とは、自分の工程はもちろんのこと、自分以外でも自分が加わっている一連のprocess全体に対し、自分事として関わり、カイケツをしてゆくこと」である。自工程完結の考え方と取り組みは、目的、目標から始まり、より未然防止に向けた活動であるために、海外、特にデミング賞を受賞したインド企業等でAdvanced Toyotaとして関心をもたれ、2018年には、創案者の元トヨタ自動車(株)副社長の佐々木眞一氏とともに、私も招へいされ、現地で「自工程完結」の講演やセミナーを英語で実施させて頂く機会もありました。 「品質」の基本定義は普遍的なものですが、2010年代から特に中部圏に居を置く自動車分野ではデジタル技術の急発展よるMAASやCASEへの新らしいビジネスモデルへの取組み、また切迫する世界的気候変動への対応等、「100年に一度の大変化」で、急変する環境変化とそれに対する具体的取り組みの再考を要する状況でした。そこで、私は「IT時代の品質保証」と銘打って研究会を創り、会員企業に参画いただき、2030年の近未来からバックキャストして、いま、これからの変化と品質保証の在り方を考察。3年間の研究会活動の知見を有志メンバーで一冊の本にまとめ「2030年の品質保証~モノからコトへ」と題して、日科技連出版社から2021年秋に出版しました。 この考察で得たことは
そこでは、「コト」と「モノ」の整理からはじめ、コトの定義とその意味する価値と其れの保証を以下のように定義しました。
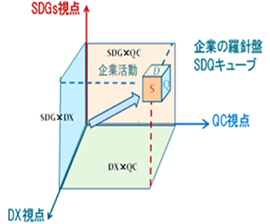 <SDQキューブとそのめざすところ>
業務工程には、SDGs、DX、QCが関係しており、個別に取り組むのではなく、総合する必要がある。 「SDGs」と「DX」と「QC」の3つの視点が最適に重なる点、そして、自らが今、それらを統合してどの位置にあるのか、向かうべきところとのギャップが視覚的にも把握しえる「SDQキューブ」という左図の概念と見える化のツールを創作した。 その名称は、SDGsのS、DXのD、そしてQCのQからとっており、それぞれの軸が3次元で重なる概念を表現するものである。 SDQキューブの考察と開発したツール、その具体的使い方について、2025年2月に「~持続的成長をめざす羅針盤~SDQキューブテンプレート実践テキスト」として執筆出版しており、講演では主要な部分を以下、図表等をお示ししながら、ご紹介しました。
報告者感想 : 今回は講演機会をいただき、ありがとうございました。当初はSDQキューブのテーマのみの講演予定でしたが、途中で「品質」との具体的関連性について質問をうけ、其の回答を冒頭の説明としてご紹介できたことが、SDQキューブの参加者の理解にもつながったのではと感謝しています。また、自工程完結の認定講師として10年ほど活動してきておりますが、クイズをだしたら、まだ半数ほどの方々には、その本意が伝わっていないこともわかり、まだまだ努力が足りないと反省もさせられました。35年以上、「日本的品質経営」にご縁をいただき、この価値観の下で実践をともない育てていただきました。「人間性尊重」は生きる礎になっており、バックキャストからみた今と未来のギャップを課題ととらえ、カイケツのプロセスを描き、品質をそこにつくりこんでゆくという活動は、平和で建設的な社会づくりに貢献すると信じ、様々な活動に取組んでいます。 SDQキューブは、企業や組織を営む皆さんと、其の為に一緒に取り組む1つの提案です。自然の恵みに感謝し、人間が自然の一部として、他の生命にも配慮しやるべきこと、誰もの喜びになることを一緒にできれば幸せです。よろしくお願いします。 |