宇宙開発におけるプログラムマネジメントの始まり
~NASAのプログラム&プロジェクトマネジメントはアポロ計画から始まる~
〇はじめに
現在、NASAは米国主導の有人月探査計画「アルテミス・プログラム」が進んでいます。一方、宇宙開発に多くの民間企業の参加が促進され、スペースX社やブルー・オリジン等をはじめとして、衛星打ち上げサービス分野や宇宙通信サービス分野ではビジネスを成功させています。
複雑で規模の大きいロケットの打ち上げや衛星のコントロールを民間企業が成功させてきている背景には宇宙開発におけるプロジェクトマネジメント(PM)とシステムズ・エンジニアリング(SE)の手法が活用され、リスクを回避させている現状があります。
今回は、NASAがアポロ計画を成功させるために、米国空軍や海軍ではすでに導入されていたプログラム&プロジェクトマネジメントの手法を取り入れ、成功に導いていきました。NASAが宇宙開発分野でこの手法導入し、独自に発達させ成功させたきっかけを考察します。
〇宇宙開発の複雑な課題はプログラムとして実施 (*1)
宇宙開発におけるプログラム&プロジェクトマネジメントが本格的に導入され始めたのは、アポロ計画(米国政府ではApollo Program)からです。
1961年、故ケネディー大統領は「10年以内に米国人を月に送り、無事に地球に帰還させる」という壮大な挑戦目標を宣言しました。この目標を達成させるには膨大な数の研究開発プロジェクトを実践活動へ展開させる仕組みが不可欠で、新たなマネジメントの手法の導入が必要でした。
月への有人飛行という戦略目的の達成には、
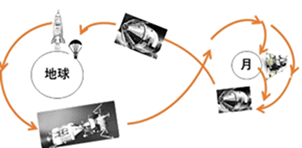
- 必要な技術やシステムや人材をどう集めるのか
- 月へどのような経路をとるのが確実で実現性があるのか
- 地球から月まで行き、帰ってくるには、
- 1) ロケットを月に向けて打ち上げ、月から地球に戻すか
- 2) 月周回軌道まで母船と月着陸船をセットで打ち上げ、月着陸船が月面まで往復するのか
の選択も必要です。
この「人間を月に送り、地球に帰還させる」という“ミッション要求”から、各種のハードウエアやソフトウエア開発、それらを統合・システム化する必要があります。
ミッション要求の実現へのツールや仕組みとするために、プログラムマネジメントとし、抱合する複数のプロジェクトとして展開・実践を行うことが必要になった。
プログラムミッション(月への往復と地球への帰還)の実現のためには、事業戦略を分析し、戦略を実践できるようにする必要があります。
プログラムミッション(使命)を明確にし「あるべき姿(To-Be)」の実現のために、現状の「ありのままの姿(As-Is)」からどのようにして到達するのかというシナリオ(道筋)を描く全体計画が必要です。これをミッションプロファイリング 1) といいます。
筆者がISS計画をNASAと調整していくときに、”ビックピクチャーを説明せよ“としばしば言われました。後から分かったのですが、”ビックピクチャー“とはミッションプロファイリングのことでした。NASAのプロジェクトを内部と国際パートナーに説明して承認をとるときに、この方法(ビッグピクチャーの何処に当たるか)で具体的なプロジェクトの内容をプレゼンで説明していましたので、ISS計画の各プロジェクトでは当たり前のやり方になっていました。
しかし、アポロ計画のころは、まだこの手法をうまく使える人材も少なく、方法も未熟だったので、プログラムとしては試行錯誤で進めていたようです。
ちなみに、アポロ計画の主要なプロジェクト群は以下のものです。
- ミッション計画と統合(ミッション定義、全体計画、要素技術開発)
- 月飛行全体システム設計(軌道選定、着陸地点選定、ロケット・宇宙船概念設計)
- 打ち上げロケットの設計・開発
- 有人宇宙船(月軌道船と月着陸船)の設計・開発
- 飛行運用管制システムの設計・開発
- 飛行運用関連(打ち上げ、飛行、月着陸、帰還運用)
- 宇宙飛行士関連(訓練計画、訓練施設建設、選抜、訓練、飛行運用)
- 安全・ミッション保証(打ち上げ安全、飛行安全、回収安全など)
〇当初アポロプログラムの状況 (*2) (*3)
このプログラムは、それぞれのプロジェクトを担当している各マネジャーには高度で複雑な技術判断を求めました。参加する人員は、ピーク時はNASA、大学、産業界合計で約40万人で、一つにまとめて行くには困難を要しました。今まで経験したことのない幅広い専門技術分野の開発を必要とし、また、プログラム進行に従って目標が変化するので、個々の目標と全体目標とを整合性のとれた状態にする必要があり、高度な判断を求められました。このような中で、最終目標である1969年末迄に月面着目標という目標に向かって、個々のスケジュールを全体スケジュールに同期させる全体計画マネジメント(プログラム)を行っていく作業でした。
ところが、NASAは発足したばかりで、研究機関や航空産業から急遽人材を集めて始動したので、“航空分野の出身”か“ミサイル分野の出身”かによって、背負っていた技術文化の違い、有人宇宙船の設計やプロジェクトの進め方が異なり、技術者間での緊張関係が生まれ、進捗は遅れに遅れていきました。
NASAのプログラムマネジャーはミサイル開発で実績をあげた方でしたが、システムズ・エンジニアリングを重視して判断、有人宇宙開発で重要な人的要素である宇宙飛行士や運用管制官の意向はあまり重視しませんでした。また、契約企業を含めて、すべて自分でコントロールしようとする傾向がつよく、内部の軋轢を多々起こしていました。
そんな状況の中、1967年1月、アポロ1号の打ち上げ施設での最終試験中に、宇宙船内部で火災が発生しハッチを開けられないまま3人の宇宙飛行士の死亡事故が発生しました。直接の原因は、配電盤に接続していた電気ケーブルの被覆がショート、宇宙船内の100%酸素に引火、宇宙飛行士3名を窒息死させてしまいました。この事故の背後にあった要因はアポロ司令船開発担当のノースアメリカン社が膨大な作業(プロジェクト)を管理し、全体のシステムを統合できなかったことでした。
ノースアメリカン社は、ボーイング社のような多くの企業が参画する技術挑戦的なプロジェクトをまとめる経験が不足していました。
例えば、司令船と月着陸船間の電波・通信系の接続を定義する「インターフェース管理」がお粗末で、各機器の検査のためにどの機器も調べることができて、紙(設計図)の上でのシミュレーションができるような仕組みになっていなかった。
また、火災事故が起こる一年前に空軍少将が、アポロ司令船の不十分な品質管理、スケジュール遅れ、コスト超過を含め数多くの問題を指摘していましたが、改善されていませんでした。
「コンフィギュレーションマネジメント 2)」も行っておらず、技術者と作業者は文書なしに、好き勝手に設計変更していた。常に膨大な設計変更がなされていたので、仕様がどんどん変化するのですが、変更契約も締結していないのにもかかわらず作業は進んでいく状態で、システムやハードを開発する企業側がついていけなかった。こういう混乱の中で、最も大事なプロジェクトマネジメントの基本ルール(進捗の同期をとる)がチーム全員に浸透していなかったのです。
〇プログラムマネジメントの改善 ~ コンフィギュレーションマネジメントの実施
事故後、NASA長官はボーイング社CEOに電話して、「アポロのシステム統合に力を貸してほしい」と要請しました。
ボーイング社は、プログラムに参加している全サプライヤー企業を統括するために、約2000人を派遣し、システムが全体として期待通りに機能するか詳細に確認を行う活動をNASAと共同して始めました。
ポイントはチェック体制で、それら作業は危機的だった状況を劇的に改善、14か月後(1969年7月)にアポロ11号により月面着陸、宇宙飛行士を地球に帰還させることに成功させました。
NASAとボーイング社が実施したプロジェクト運営改善の例として「コンフィギュレーションマネジメント」について紹介します。
NASAの新プログラムマネジャーは、司令船の設計について、火災の要因を洗い出し対処していきました。地上試験では酸素と窒素の混合気体(空気と同じ割合)に切り替え、できるだけ難燃物に置き換え、ショート防止のために電線に被覆加工を施しました。ハッチは内側からも外側からも開閉できるように再設計し、安全面での脅威が残らないよう徹底的な審査を行う安全審査を設定し、実行しました。
また、並行して「コンフィギュレーションマネジメント委員会」の権限を強化し、毎週金曜日正午から夜中まで、設計変更に関する意見をすべて聞き、一つ一つ丁寧に判断を下していきました。このコンフィギュレーションマネジメント委員会がプログラムの実質的判断の場となりました。
その後、NASAは、国防総省のガイドや規則を随時とりいれたプログラム&プロジェクトマネジメントルールを調達手法として取り入れていきましたので、NASAの仕事をする民間企業は否応なく対応せざる得なくなるように仕組みを変え、結果として、成功を収めました。
科学技術が巨大化し、高度化し、分業化されると、システム全体が見えにくくなり、そして、担当領域がより専門化・細分化され、システム全体をまとめる経験ができない方が多くなって来ています。
プログラムとして全体を把握する力を付けるには、まずはプログラム&プロジェクトマネジメントの手法を学ぶことがNASAやJAXA、多くの企業で求められています。
プログラムマネジメントで、これだけの成功を治めた、ボーイング社の現状、心配になりますね。人に関わるプログラムマネジメントのノウハウは人が変わる(引き継ぐ)度に劣化していきます。
最近のように、AIが発達しても、最後の判断は “ 人間 ” です。判断には知見が必要です。
このことを念頭に置き、チーム員への技術継承を含めて事業を進めて行かなければならない、ということです。
8月号にも書きましたが、伊勢神宮の遷宮(20年毎)のようなノウハウの伝承の仕組みが必要です。
参考文献
| (*1) |
清水基夫著、「実践プログラム&プロジェクトマネジメント」、JMAM,2010年 |
| (*2) |
佐藤靖著、「NASAを築いた人と技術」、東京大学出版界、2008年 |
| (*3) |
デビッドミンデル著、「デジタルアポロ」、東京電機大学出版局、2017年 |
1) ミッションプロファイリング (Mission Profiling):
プログラムを組み立てる初期段階で、事業戦略を分析し、戦略を実践できるように、プログラムミッション(使命)を明確にし、「あるべき姿」へ、現状の「ありのままの姿」からどのようにして到達していくのかというシナリオ(道筋)を描くプロセスである。 |
2) コンフィギュレーションマネジメント (Configuration Management):
システムのライフサイクルにわたる範囲、性能、機能的および物理的要件、設計、操作に関する情報などを確立し維持するプロセスです。形態管理とも呼ばれます。最初は、米国国防総省が1950年代に武器システム、車両、情報システムなどを管理するため開発したものですが、今や国際標準で定義されるようになり宇宙航空、ITサービス管理、道路・橋・運河・ダム・建築物の建設・保守管理や生産技術などで使用されています。 |
|