宇宙にもガソリンスタンドが出現するかも?
~ 衛星の長寿命化への挑戦 ~
〇はじめに
1月29日、ノースロップ・グラマン社は衛星が給油衛星から「宇宙給油」を受ける際に装備すべき仕様について、米国宇宙軍から衛星用給油設備の認証を得たと発表しました。また、米宇宙軍は宇宙デブリ除去を目指す日本のスタートアップ企業の米子会社「アストロスケールUS」と衛星の燃料補給開発契約を結び、2026年までに燃料補給衛星の試作機を提供すると発表しました。さらに、米宇宙軍は、スタートアップ企業「オービット・ファブ社」、「クリアー・スペース社」及び「アストロスケール社」と連携して、宇宙軍の宇宙給油プロジェクトを推進しているとも伝えています。 (*1) (*2)
宇宙給油の難しさは、相手の衛星の動きを推測しながら接近していくので、大量の画像データを高速処理するコンピュータと回転している衛星を捕獲し静止させる技術が必要なことです。今回は宇宙給油の現状を紹介します。
〇すでに宇宙給油実証は行われている
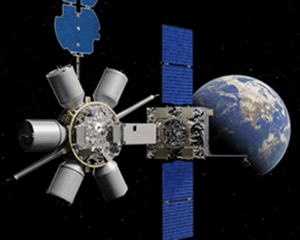 現在の静止衛星の多くは衛星の軌道や姿勢を制御するための燃料が枯渇してミッションを終えています。静止衛星は、非常に利便性の高い地上高度3万6千キロの軌道です。そこにピタリと衛星を投入できると、どんな衛星でも地球の自転と角速度が同じになり、地上からみて空の一点に留まることができるので、気象衛星「ひまわり」やBS、通信衛星、軍事目的の衛星が列をなしています。
現在の静止衛星の多くは衛星の軌道や姿勢を制御するための燃料が枯渇してミッションを終えています。静止衛星は、非常に利便性の高い地上高度3万6千キロの軌道です。そこにピタリと衛星を投入できると、どんな衛星でも地球の自転と角速度が同じになり、地上からみて空の一点に留まることができるので、気象衛星「ひまわり」やBS、通信衛星、軍事目的の衛星が列をなしています。
現在の通信衛星の寿命は約15年で、燃料切れがその主要因です。衛星の寿命を延ばし、コストダウンのために宇宙給油が望まれています。
宇宙給油には、
- 衛星への接近・ドッキング技術
- ドッキング後に衛星に燃料を届ける補給技術
の二つの主要技術が必要です。
宇宙軍から認証を受けたノースロップ・グラマン社の「燃料タンクへの注入インタフェース」は特許を取得済みで、世界の先頭を走っています。(右図はグラマン社の燃料補給衛星の構想)
2020年2月、スペース・ロジステック社の衛星「MEV-1」が、2001年から19年間運用され位置制御用燃料が不足していた「インテルサット通信衛星」にドッキングし、2025年までの運用寿命を延ばしたと発表しました。
また、2021年4月には、同社の衛星「MEV-2」が、2005年から15年間運用している別のインテルサット衛星にドッキング・給油し、約5年間の延長を実現しています。
オービット・ファブ社の「衛星燃料補給ポートのオープンライセンス規格」は、米国防総省を含む複数の政府機関や100以上の商業団体が採用しています。
オービット・ファブ社は、米宇宙軍と2024年にスタートする衛星への燃料補給と軌道上のドッキング・デポの開発について契約し、技術開発もすでに始まっています。
2019年、ISSの内において、燃料に見立てた液体の輸送を装置間で成功し、2021年7月に1号機の燃料タンクを地球周回軌道に打ち上げています。
〇衛星への接近技術は飛行機とは違う
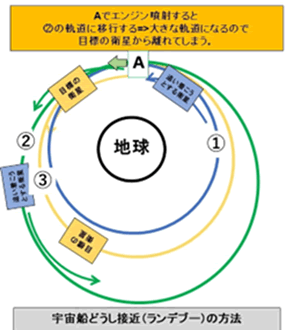 1965年、NASAはアポロ計画に先立ち、衛星間の接近技術(ランデブー)のテストのため、ロケットの第二段をターゲットにして、同じ軌道で接近させようとしました。
1965年、NASAはアポロ計画に先立ち、衛星間の接近技術(ランデブー)のテストのため、ロケットの第二段をターゲットにして、同じ軌道で接近させようとしました。
操縦する宇宙飛行士は戦闘機のベテランパイロットでしたが、彼はターゲットが見えたので、後方エンジンを噴射させました。しかし、ロケットは遠ざかっていきます。
なにかおかしいと思いさらに何回かエンジンを噴射させました。しかし、なぜかロケットはますます遠ざかっていきました。(右図の①→②)そのため、燃料を多く消費してしまいました。
彼は、飛行している場所が慣性空間であることを忘れていました。宇宙空間では、ターゲットに追いつくにはケプラーの法則に従って操作しなければならないのです。
わかりやすく説明すると右図のように地球を周回する宇宙船に、後ろから追いつくには軌道円を①→③の橙の円に移る必要があるので、Aの地点で前方のエンジンを噴射してブレーキをかけ宇宙船の速度を減速し、楕円軌道を小さくしてターゲットを同じ軌道円にしなければならないのです。 (*3) 現在この技術を保持しているのは、米ロ及び欧州、中国、および日本です。
| ※ |
慣性空間:無重力、真空、といった条件により外部から力を加えない限り、物体の運動になんの変化も起きない空間 |
〇宇宙給油や軌道上サービスを巡る動き
- スペースX社は、有人月探査「アルテミス計画」で有人月着陸船の開発をNASAより受注しています。まず月面までの燃料を搭載した燃料貯蔵用のスターシップを事前に地球周回軌道に投入しておき、次に月面着陸用のスターシップを地球から打ち上げ、地球周回上で燃料補給したのち、月宇宙ステーションに向かいます。
- アストロスケール社は2021年3月に宇宙デブリ除去衛星を打ち上げ、模擬デブリ捕捉や誘導接近に成功しています。
デブリ除去や寿命延長サービスをJAXAとの間で、パートナーシップを締結して、商業デブリのための機器をもっていない物体に接近、その物体の運動や損傷の度合いを映像で撮影しています。 (*4)
衛星は、使い捨ての常識が変わろうとしています。
私の現役時代にハッブル宇宙望遠鏡衛星の高機能化が5回に渡り実施されました。それは、スペースシャトルによる衛星への接近・ドッキング、宇宙飛行士の船外活動で機器の交換作業によりアップグレードが実施されました。ハッブル宇宙望遠鏡の性能が向上し、未知の天体が多く発見されたのを覚えています。
宇宙飛行士が複雑な作業を長時間にわたって行っているのをNASAからのTV映像で見ながら、予め設計の段階で機器類を変えられるようにしていれば、衛星が古くなったらアップグレードすることで長く活用できるのを実感していました。宇宙で燃料補給したり、機能を追加したりして寿命を延ばす試みが具体化しつつあるのは自然の流れですね。
参考文献
|