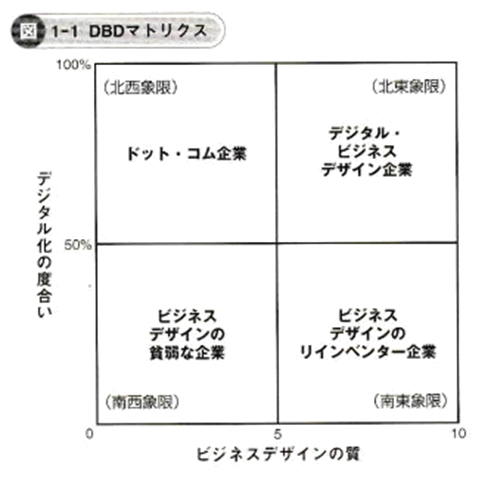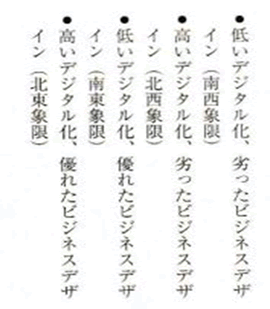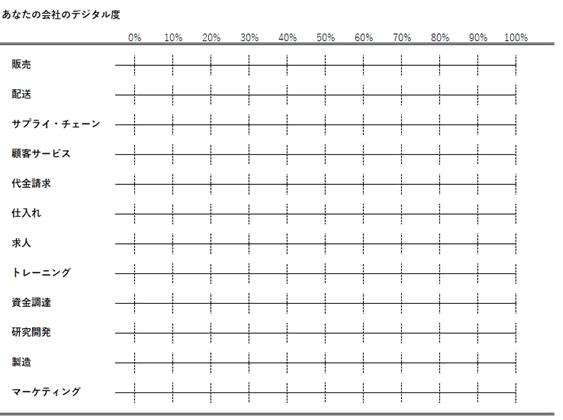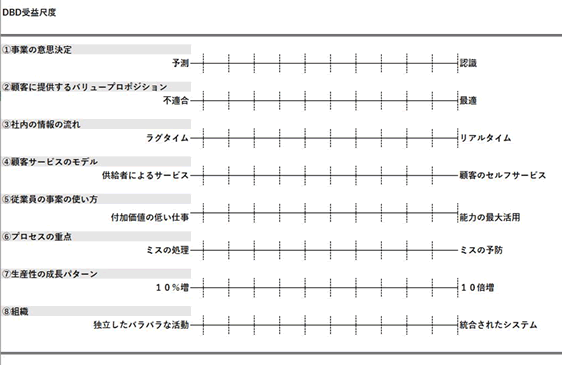【平成時代の政治活動とそれと異なる令和に向けた大胆な戦略の構築】
P2M研究会 芝 安曇 : 11月号
- Ⅰ.11月号の発刊となった。
ここで真っ先にお詫びしておきたい。9月号は真っ先に「DBD」の説明から入りたかったが、財務省の意向はデフレに対する次の政策は民主党からの消費税公布であった。これに対するアベノミクスがわの主張は、最初から一貫して脱消費税不要であった。最後は国会の焦点を、アベノミクスの成長のありかたで、第一の矢(金融)を軸とした政策で、日銀黒田総裁の金融論が最初の5年間で楽勝と思っていたが、緩やかなインフレにもなれず、二期目の5年間でも成功しなかった。結果として国会ではリフレ派(金融緩和派)第二の矢支持者が強くなり、植田日銀新総裁もリフレ派に同意した。最終的には安倍総理はリフレ派の提案に寛容になっており、反対しなかった。この時点でアベノミクスはリフレ派の方針で進めることになった。目標は5年間で1%に格下げが認められた。
- Ⅱ.アベノミクスの行方はどうなる? 芝 安曇
安倍総理のアベノミクスに対する大いなる献身に敬意を表します
PMAJ機関紙 のオンラインジャーナル 読者の皆さん
アベノミクスのメンバーで成果を出せるか気になっていました。
20年前に 「デジタル・ビジネスデザイン戦略」初版2001年11月15日
著者エイドリアン・スライウオキ+デイビット・モリソン
監訳者成毛 眞、訳者佐藤徳之 が発売になっていました。
私はこの本に触れて米国がインターネットを開放してから5か年強で、この本に書いて、米国らしい世界観を示したことに恐れをなした。
時に米国はこの本を出版した経緯は、重工業を抑えながら、重工業から逸脱し、二つのことをした。これからの世界は「軽く、早く、知的な活動で世を制するよと言っていた」。確かに世界を一変させた。米国という国はインターネット敷設から発想が豹変した。
2000年の日本はバブルで意気上がらない時代だった。米国は一時期ドラッカーの時代であったが、アメリカも変わった。今のアメリカはアングロサクソンではなくなってきた。
そこで今回は「デジタル・ビジネスデザイン戦略」読んでみた。
第1章 デジタル・ビジネスデザインとは何か
- ▼ デジタル・ビジネスデザインの質とデジタル化の度合い
「DBD]とはデジタル技術を用いて、企業の戦略の選択肢を拡大させるある種のアートであり、サイエンスである。DBDそのものはテクノロジーそのものを指すのではないが、顧客に与える恩恵、持続的な成長率、人材開発力、財務実績という点で、僅か数年前まで不可能と思われていた案件を成し遂げ、大きな富の開発に成功している。
- ▼ デジタル化に対する誤解
この20年間で企業やその指導者たちは、「デジタル化」が人々の仕事、娯楽、通信、購買、販売、生活に変更をもたらしつつあり、1部は破壊的活動力でもあり、また想像的な力だと気が付くようになった。認知の時期は様々でその引き金となったのは、パソコンの出現、電子メールの発達、統合業務のパッケージシステムの成功などである。
顧客の要求を満たしたりユニークなバリュー・プロポジションを生み出したり、人材を活用したり、生産性を抜本的に向上させたり、利益の拡大を指す。デジタル化の選択肢を用いて優位性だけでなく「ユニークな」ビジネス・モデルをつくり上げていることに専念するようになった。
デジタル・ビジネスは顧客に与える恩恵、持続的な成長率、人材開発力、財務実験という点において、僅か数年前まで不可能と思われていたものを成し遂げる。
デル・コンピュータとコンパックは、同一業界で同様の製品を生産している。だが、デルはデジタル・ビジネスであり、コンパックはそうでない。その違いは何か。デルは次のような点でユニークなのだ。
●自社の顧客のニーズを知り、彼らが本当に求めるモノを与える度合い
●収益性が低下する業界において、達成している傑出した財務実績
●自社の事業に於いて獲得した、比類なき水準の戦略的コントロール
がデジタル・ビジネスデザイン(DBD)のこうした現象に同化して欲しいと願って研究を進めた。そこで考えたのが「デジタル・ビジネスデザインとは何か」であった。
「DBD」とはデジタル技術を用いて、企業の戦略の選択肢を拡大させるある種のアートであり、サイエンスである。DBDそのものはテクノロジーそのものではないが、顧客に与える恩恵、持続的な成長率、人材開発力、財務実績という点で、僅か数年前まで不可能と思われていた案件の成し遂げで大きな富の開発に成功している。
「◎ここでの課題はビジネスデザインの質とデジタル化の度合いであった」
- ▼ ではコンパックは他のパソコン・メーカーと同様、自社製品の販売を、ほとんど小売り販売店に依存している。
デジタル・ビジネスデザインによって、企業はずっと実現不可能と考えられていた目標を達成することができるのに、一般の企業は少なくとも理屈では、従業員の時間や能力の浪費は罪であるという前提を認めているが、低価格な仕事に実に多くの時間を費やしている。
- ▼ デジタル・ビジネスデザインのマトリクス
図1-1 DBD マトリクス
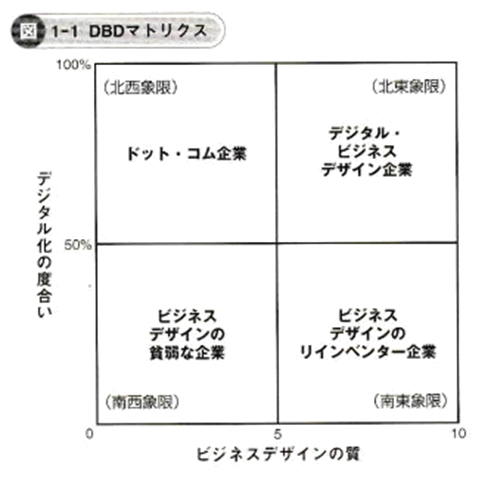
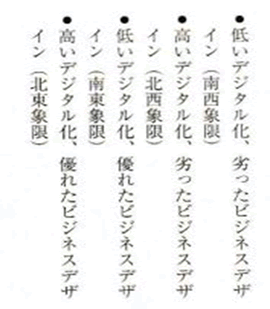
- ほとんどの企業は「南西象限」に含まれるが、彼らは貧弱なビジネスデザイン、すなわち根本的に欠陥が有り、既に起こっている変化に対し明らかに脆弱なビジネスデザインしか持っていないため不利な立場にある。
- ドツト・コム企業のほとんどは、この北西象限に属する。デジタル化の度合いは高いものの、ビジネスデザインに欠陥が有ったり、不完全だったりするため不利な立場にある。
- 南東象限には、GEやスウオッチのような、デジタル化の度合いは比較的低いが、優れたビジネスデザインを持つ企業が含まれる。我々は前著『The Profit Zone』(邦訳)『プロフィト・ゾーン経営戦略』ダイアモンド社)において、こうした企業を「リインペンター(ビジネスの再創造者)と名付けた。こうした企業はいずれも経営陣が優秀で勇敢であるために、驚異的な成功を収めている。彼らは、価値連鎖の中ででも巨大で成長しているセグメントを獲得し、支配するビジネスデザインを創り出し、その後、そうしたデザインを必要に応じてリインベント(再創造)して、顧客の優先事項、テクノロジー、社会的及び経済的状況、競争相手などの変化に対応したのである。だが、今や次のような事実が明らかとなった。
- ● 自社のデジタル度を知る「北東象限」
在来形の企業からDBD企業への移行は「北東象限」である。デジタル・ビジネスデザイン企業への移行を果たした少数の企業が属する領域に見られる。社内の主要活動の多くを書類主体の処理からデジタル処理へと移行させることにある。事業のデジタル化の少なくとも部分的な尺度を得るために、われわれが「デジタル度の評価」と呼ぶ、2分間の演習をおこなって欲しい。DBD企業へと移るプロセスをはじめる前にこれを用いれば、基準となる値が得られ、移動のどの段階にあっても進度を図ることで良い感覚がでる。
- ● 自社の顧客のニーズを知り、彼らが本当に求めているものを与える度合い
- ● 収益性が低下する業界において、達成している傑出した財務実績
- ● 自社の事業において獲得した、比類なき水準の戦略的コントロール
- ◎ 本書では、北東象限へ移行した草分け的企業である、デル・コンピュータ、セメクス、チャールス・シュワブ、シスコシステムズの四社を詳細に検証する。
これらの企業がデジタル・ビジネスデザインを用いて業界での圧倒的な立場をどのように獲得してきたかを考察し、更には彼らを模倣し始めた企業にも目を向ける。
顧客のニーズに関する予測は感と経験で活動するが、このような習慣をやめる方法はデジタル・ビジネスデザインによって簡略化できる。DBDは、このような以前はどうしようもなかったジレンマの解決に役立っている。
顧客の要求を満たしたり、ユニークなバリユー・プロポジシヨンを生み出したり、人材を活用したり、生産性を抜本的に向上させたり、利益の拡大を指す。デジタル化の選択肢を用いて優位性だけでなく「ユニークな」ビジネス・モデルをつくり上げることに専念するようになった。
図1-2 あなたの会社のデジタル度
- ▼ 自社のデジタル度をしる。
在来の企業からDBD企業へのーすなわち、北東象限へのー移行における重要な側面の一つに、社内の主要活動の多くを書類主体の処理からデジタル(通常はオンライン)処理へと移行させることがある。事業のデジタル化の少なくとも部分的な尺度を得るために、われわれが「デジタル度の評価」と呼ぶ、二分間の演習をつて欲しい。DBD企業へと移るプロセスを始める前にこれを用いれば、基準となる値が得られ、移行のどの段階にあっても進度を図ることができる。また四象限図上であなたの会社を正確に位置図けるうえでもやくにたつ。結果として出たチェックマークは、ほとんどが表の左寄りであればデジタル化の選択肢の活用を広げることができる。これができれば図1-2あなたの会社デジタル度を上げることができる。
DBDは表面的には、あなたの事業のプロセスのいくつが、オンラインで行われているかを示す。だが、より深いレベルにおいては、あなたがデジタル技術によって新たに可能となった戦略上の選択肢を活性化して事業のやり方を変えたかどうかを示している。
自社のデジタル度を測ることは有益な演習である。多くの企業にとっては、粛然とさせられるものなのだろう。だがそれだけではDBDが本当に意味することの表面をなぞったに過ぎない。
- ▼ DBDの真の恩恵
図1-3 DBD受益尺度
- ● DBDの真の恩恵
- ① 事業の意思決定の証拠を「予測」から「認識」へ
- ② 顧客に提供するバリュー・プロポジシオンを大小の「不適格」から「最適」へ
- ③ 社内の情報流の流れを、「ラグタイム(遅延)」から「顧客のセルフサービスへ」
- ④ 顧客サービスのモデルを、「供給者によるサービス」から「顧客のセルフサービスへ」
- ⑤ 従業員の時間的の使い方を「付加価値の低い仕事」から「能力の最大活用」
- ⑥ 様々なプロセスの重点を、「ミスの処理」から「ミスの予防」へ
- ⑦ 生産性の成長パターンを、「10%増のノルマ」から「生産性10倍増」へ
- ⑧ 組織を、「独立したバラバラな活動の寄せ集め」から、情報、考え方、解決法を共有する「統合されたシステム」へ
事業のやり方におけるこうした移行は、顧客、人材、利益に重点を置いているため、それこそがDBDの真の成果である。事業のプロセスの重要な部分をデジタル化することは必要かつ重要なステップだが、それは目的ではない。事業の変化に関する八つの尺度は、プロセスがどれだけデジタル化されているかだけでなく、その移行から顧客や人材や投資家がどれだけ恩恵を受けているかを示す測量単位でもある。そのため、これらの尺度における動きは、北東象限への動きをより正確に映し出すことになる。
図1―3のDBD受益尺度であなたの会社を測定してみよう。図1.2のデジタル度の場合と同様、素早く行うようにしたい。こちらの書き込みにはもう少し時間がかかると感じるかもしれない。だが、迅速な直観による返答によって90%の精度が得られるのだ。この尺度において、あなたの会社のビジネス概要はどう表れただろうか。主として図1-3の左右どちら側に寄っただろうか。どのくらいの速さで左から右へと動いているだろう。主要競合企業の特徴はどこにあり、彼らはどのくらいの速さで動いているだろうか。顧客の期待はどのくらいの速度で変化しているだろう。
次の問いについても考えてもらいたい。
- 主として尺度の右寄りにいる企業の財務実績はどのようなものになるだろうか。
- 左寄り、右寄りといった言った位置に関連して、従業員の勤労意欲、仕事の満足度、会社への長期的なコミットメントは、どのようになるのだろうか。
- 顧客満足度が増すのはどこだろうか。
- どちらのビジネスもでるモデルだ長期的な投資家を引き付け、保持しそうか。
こうしたDBD受益の真の効果は、加法的でなく「倍数的」である。それぞれの左から右への移行は事業の方法を著しく向上させ、顧客、人材、投資家が一様にそれに気づき、報われることになる。それぞれの移行はまとまって、全く新しい事業のやり方を生み出す。
自社について考える際は、本章に登場した図表を用いて変革のための計画を作成して欲しい。自社の現在位置をチェックマークで示したら、次は12か月後までに動かしたい位置を「T」で示すのである。続いて、次の三つの問題について考えていきたい。
- ① 自社が直面する具体的な事業課題を考えると、特に重要な動きはどれだろうか(顧客の立場からすると、何が最も重要だろうか。人材的側面からは何か。経済的側面からは何か)
- ② 改善の順序としては、どうするのが適切か。
- ③ あなたの組織では、いくつの構想を並行した行うことができるのか。
我々は、以後、本書を通じてDBD受益尺度に言及していく、そこで紹介されるデジタル・イノベーターが、いかに考え方や事業のやり方を変えてきたか理解するうえで、彼らが予測から認識へ、顧客のニーズとの不適合から最適へ、ラグタイムの活動からリアルタイムの活動へ、といったように、どれほど尺度の左側から右側へ動いたか理解するのも一つの方法だろう。
デジタル・ビジネスへの移行初期段階である現在においても、そのようなデジタル化の恩恵が十分に実現されると知って驚くことになるかもしれない。
- ▼ デジタル・イノベーションを生み出だすもの
最後にもう一つ述べておきたい。すべてのデジタル・イノベーターは、ある共通した資質を有している。すなわち彼らは、顧客、従業員、投資家に対する「精力的な擁護者」なのだ。彼らの考え方は極めて単純で、次のような一つの問いに対する答えを驚くほど粘り強く追い求めている。
デジタル化の選択肢をいかに活用すれば、顧客によりよい取引を提供できるか。従業員にとってより良いシステムを創り出せるか。投資家にリスクを調整したよりよい利益を生み出せるか。
こうした三つの問題に絶えず集中することで、いくつかの素晴しいビジネスデザインが生み出されている。細部は異なるものの、どれも事業課題と顧客の問題から始まったのである。
12月号は
第2章 デジタル。ビジネスデザインの出発点
● DBD移行への五つの課題
から話をすすめる。
|