|
「第287回例会」報告 枝窪 肇 : 10月号
【データ】
日頃、プロジェクトマネジメントの実践、研究、検証などに携わっておられる皆様、いかがお過ごしでしょうか。今回は、8月に開催された第287回例会についてレポートいたします。 ~はじめに~ プロジェクトを実践する多くの会社では、PMO業務を行う部署を設置し、プロジェクト遂行を支援していることと思います。私(筆者)の会社でもPMO部署がプロジェクト遂行のために色々な支援を提供しています。 今回のご講演では、大規模プロジェクトのPMO経験が豊富な講師から、自らの経験を踏まえたお話を伺えるということで、プロジェクトをうまく運営するための具体的なヒントを得られると期待しながら拝聴いたしました。 ~講演概要~
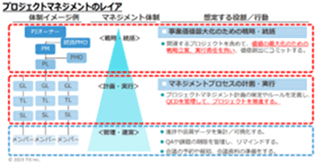 〇 プロジェクトの成功とは? 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が、「Q(品質)」「C(コスト)」「D(納期)」の3つの側面で2019年のデータをもとに総合評価したところ、情報収集したプロジェクト全体の59%は「成功」、残る41%はQCDのいずれかで「失敗」という結果であった。 QCDを管理してプロジェクトを推進し、PMをサポートするのがPMOならば、その役割はとても重要である。 〇 プロジェクト管理のコツ、勘所 ・ 立ち上げ前
~筆者所感~ 今回の講演では、PMOがプロジェクトや遂行メンバーを支援する際に、どのような観点を大切にし、また、陥り易い罠にかからないようにどのようなチームを醸成しているかが理解できました。自分がPMOとして活動するときにはもちろんのこと、PMやプロジェクトメンバーとしてプロジェクトを遂行する立場の時でも気を付ける/心がけるべきことがわかり、PMOの手を煩わすことなくプロジェクト成功に近づくヒントも得られたと思います。 例会という機会を通じて貴重なお話ししていただけたことに、心より感謝を申し上げます。 ご講演の資料は協会ホームページの「ジャーナルPMAJライブラリ」の月例会開催資料に、発表資料をアップロードしていますので個人会員の方はご参照いただければと思います。 なお、我々と共に部会運営メンバーとなるKP(キーパーソン)を募集しています。ご興味をお持ちの方は、日本プロジェクトマネジメント協会までご連絡下さい。 以上
|