●筆者の作曲の「やり方(具体的方法論)」の紹介
世の中で「作曲」を趣味(道楽)にしている人は、筆者が知る限り、あまりいない様である。また「作詞」を趣味(道楽)にしている人も、やはり少ない。何故だろうか? 恐らく、多くの人は作曲や作詞と聞いただけで「身構え」てしまうからだろう。
筆者は、既述の通り、作曲の「道楽」が高じてプロ作曲家となり、その様に認められた。しかし何故、認められたのか? 思い返してみると、「好きこそものの上手なれ」である。大好きな事をひたすら続けて、そこそこ上手になった結果、「幸運」が舞い込んで来た為であった。「幸運」は誰にでも必ず訪れる。従って筆者の場合は例外ではない。「夢」を持って、大好き事を続ければ、「幸運」が必ず訪れ、何らかの「成功」を果たし、「夢」を叶える事ができると「夢工学」は力説する。
出典:作詞家:clipground.com/songwriter-clipart.html
作曲家 Compositor, La Música, Dibujo imagen png - imagen
「何故、作曲するのか?」と云う「在り方(基本的考え方)」は人様々である。その「様々な人達」の一人として筆者は、自身の作曲の「在り方」を前号まで解説した。
「如何に、作曲するか?」と云う「やり方(具体的方法論)」も人様々である。その「様々な人達」の一人として筆者は、自身の作曲の「やり方」を今月号から解説する。
さて作曲の「在り方」は文章や絵などで表現できる。しかし作曲の「やり方」は文章や絵などで表現するには限界がある。ピアノを弾きながら作曲の「やり方」を見せれば、直ぐに理解される。しかし本稿でそれが出来ない。これが筆者の悩みである。「何とか工夫」して解説したい。
●音楽理論書、作曲法専門書、音楽雑誌など
世の中に音楽理論、作曲論、作曲方法などの専門書、雑誌、記事などが数多く存在する。其れ等は有名な作曲家、著名な音楽大学教授、人気の演奏家などに依って出版されている。
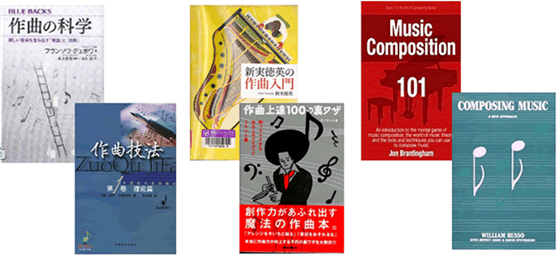
出典:上記の書籍:筆者の所蔵本、一部は豊島区中央図書館所蔵本
筆者は昔から音楽専門書や作曲専門書などを本職の合間と隙間で色々読んできた。しかし日本の専門書はクラシック音楽が中心である。その為、クラシック音楽の歴史、クラシック音楽理論、クラシックの作曲に必要な和声、旋律、リズムなどの理論がいろいろ紹介され、詳しく書かれている。しかし筆者の道楽のジャズ理論書は少なく、詳しい内容を知る事は限定的である。
どの音楽専門書や作曲専門書でも、肝心の作曲する場面で、具体的にどうすれば、優れた、美しい、自分が気に入った旋律を生み出せるのか?と云う部分の解説がハッキリしていない。作曲は、理論、理屈、形、記述などでは伝授できないのか? 現場で立ち合っても中々教えられないのか? どうもその様である。筆者も作曲方法を尋ねられたり、指導して欲しいと要請されると、いつも苦労する。この事はビジネスの世界でも同じである。被指導者に経験知、体験知などを「心得&体得」させるは大変な困難を伴う。「優れた作曲」を「優れた発想」と言い換えれば、誰しも分かるだろう。
しかしビジネスの世界では数多くの「発想法」が開発され、活用され、効果を上げている。しからば音楽の世界で何故もっと多くの「作曲の発想法」が開発され、活用されていていないのだろうか? 不思議である。因みに筆者は作曲に行き詰まった時は、「デック思考(夢工学式発想法)」を活用して作曲している。
それにしても、「作曲の方法は教えられない」と自分で書いた「作曲論」の中で主張している某作曲家がいる。ならば「何故、あなたは作曲法の本を書いたのですか?」と言いたくなる。いずれにしても、「作曲法」に関する本、雑誌などが巷に溢れている。しかし残念ながら怪しげな内容のものが多く、殆ど参考にならない。
以上の状況から①「筆者式作曲のやり方」を解説する事、②「何とか工夫」しながら「やり方」を解説する事、③前号までで紹介した作曲の「在り方」に従って「やり方」を解説する事にしたい。
もしこれ等の解説が参考になり、「作曲できそう」と感じたら、「チャンス」である。その場で楽器を弾いて作曲する。楽器を弾けない又は弾く環境にないならば、思い浮かんだ旋律を声に出して作曲する。作曲した旋律を楽譜に書けない又は書ける環境にないならば、スマフォの録音機能に記録する事である。
数小節の作曲でOKである。思い付いた部分をその都度、記録する事である。デック思考が薦める「アイデアをメモする事」と同じである。後でそれを引き延ばし、展開すれば、立派な曲になる。
出典:作曲 iconfinder.com/i2277287/composing_music_musician_writing_icon
スマフォ録音 dreamstime.com/mobile-phone-recording-image36200480
もし作曲された部分の楽譜か、スマフォ音声情報か、どちらかをPMAJ事務局を通じて筆者に送ってくれれば、希望に応じて、その部分を基に「1曲」完成させる事を約束する。
「チャンスは貯金できない」。アサヒビール元会長・樋口廣太郎(1926~2012年)が住友銀行出身者らしく語った言葉である。チャンスは生もの、いつまでも存在し得ない。いつでも、どこでも自由に使えない。チャンスはその時に現れ、前触れもなく消える。従って思った時、気付いた時、やりたいと決心した時、その「時」が唯一無二のチャンスである。筆者の上記の約束は「貯金できない」。今が「チャンス」である。作曲に挑戦してはどうだろうか。
●筆者の作曲の「在り方・その1」=昔も、今も音楽が大好きであること。特に作曲する事を最も好み、最も得意でもある。
筆者は子供の頃から曲を作る事を最も好んだ。何かを頭の中に描くと、不思議な事に曲が幾らでも湧いて来た。此の妙な習性は今も変わらない。この事を以前の号で書いた。
筆者と同じ様に曲が湧いて来る習性を持った人物が本稿の読者の中にいると思う。その様な人物には筆者の作曲の「やり方」を解説する必要はないだろう。その様な人物はとっくの昔にプロ作曲家になっているだろう。
自分で作詞、作曲した歌を自分自身で唄う為に、筆者が出演するジャズライブハウスに来店し、筆者のバンドの伴奏でカッコ良く、Coolに唄う中年の男性客がいる。筆者はコロナ危機でバンド出演を中断し、その客との音信が途切れた。しかし来月の8月から有名且つ老舗の某ジャズライブハウスで出演を再開する。彼に唄いに来て貰う積りである。
以上の様な習性を持たない人物、作詞・作曲する人物ではないが、音楽に興味があり、本稿を読んで作曲をしてみたいと思った人物は、このチャンスに是非、作曲に挑戦してはどうだろか。何故なら「楽しい」からである。最初は楽しくないかも知れないが、作曲すると楽しくなるからだ。
そもそも「趣味(道楽)」は、どの種類のものでも、始める時、始めた後も、かなりの「カネ」が掛かる。しかし「作曲」は、終始「カネ」が掛からず、「楽しい」だけだ。おまけに「カネ」を稼ぐ事もできる。作曲はお薦めの「趣味(道楽)」である。勿論「作詞」もカネが掛からない。作曲家と組めば、自分で唄えてもっと楽しい。
●作曲の「やり方」を解説した「或る本」
この本では作曲の方法として以下の事が書かれている。
- 1 作りたい曲のイメージを決める事
- 2 メロディを考える事
- 3 作ったメロディをコード進行に合わせる事
「作りたい曲のイメージを決める」とは、次の事をする事を云う。明るくて元気の出る「幸福」を感じるメロディを作曲するのか? 失恋をテーマにした悲しい「不幸」を感じるメロディを作曲するのか? など作りたい曲のイメージ(気分、雰囲気など)を想像する。この事で自分の作曲したい気持ちにスイッチが入り、メロディが浮かび易くなる。

出典:幸福と不幸 Happy and sad face icons Royalty Free Vector Image
「メロディを考える」とは、以下の事をする事である。
- 1 自分の気持ちや感性を頼りにメロディを作る事
- 2 音楽理論を学び、明るい響きと暗い響きなどを言語化(旋律化)できる作曲力を駆使する事
- 3 鼻歌でも、ピアノなど楽器を使ってメロディを考える事。
- 4 覚えやすいキャッチーなメロディを作る事
- 5 メロディは短時間で終わるCMソングの長さで作曲する事
- 6 「ドレミファソラシ」の全ての音階を一挙に無理矢理に使わず、「ドレミ」や「ドミソ」など3つから5つくらいの音を使ってメロディを考える事
- 7 まとまりのあるメロディを作る事
- 8 最初は簡単なメロディも作る事が難しいが、続ければコツを掴める。毎日少しでも作曲する事
「作ったメロディをコード進行に合わせる」とは、以下の事をする事である。
- 1 作曲に必要な事は、作ったメロディをコード進行に合わせる事
- 2 コード進行とは、コードを順番に鳴らすことで、曲の雰囲気や展開を演出する響きの事
- 3 コードとは、3つ以上の音が重なった状態を云う事
- 4 起承転結のメロディだけでなく、コード進行の変化に合わせた作曲をする事
- 5 コード進行のパターンは少なく、いくつかのパターンを覚えて、作曲に活かす事
- 6 コード進行に合わせてメロディを作曲し、それを演奏すると曲の輪郭が明確になる。だからコード進行からメロディを作曲する事
- 7 作曲アプリ等を活用すると、初心者でも簡単な曲なら作曲可能。挑戦してみる事
この本が薦める上記の「作曲のやり方」で、「試しに」、作曲の「トライ」をしてはどうだろうか?
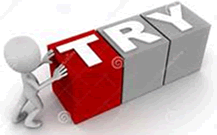
出典:トライ dreamstime.com/royalty-image-try-word-blocks
つづく

