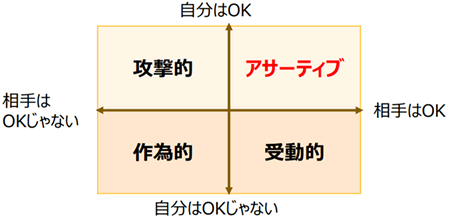|
「第284回例会」報告
例会部会長 枝窪 肇 : 7月号
【データ】
| 開催日時: |
2023年5月26日(金) 19:00~20:30 |
| テーマ: |
チーム力を高めるためにできること
~ひとりとの信頼関係からはじめよう~ |
| 講師: |
吉田 則子 氏/プロジェクト・カウンセリング・オフィス cocokara代表 |
日頃、プロジェクトマネジメントの実践、研究、検証などに携わっておられる皆様、いかがお過ごしでしょうか。今回は、5月に開催された第284回例会についてレポートいたします。
~はじめに~
大抵の人はいくつかのチームに属していると思います。私(筆者)も所属する会社の部署はもちろん、組織をまたいだ複数のタスクフォースチームや、社外ではPMAJの例会部会等の活動チームに属しています。
今回のご講演では、チーム力を高めるためにできることのヒントをご教授いただけるということで、コロナ禍で疎になったコミュニケーションを再び密にするためのヒントなども得られるのではないかと、期待しながらお話を伺いました。
~講演概要~
- 本日の講演でお伝えしたいこと
今回のアブストラクトにも書いたとおり、医薬品開発とはまったく畑違いの自動車エンジン開発のプロジェクトで、プロジェクトマネジメントをきちんと遂行することができるようになることを目的としたコンサルタントを引き受けた際の経験の中で学んだことを、理論と私見を交えてヒントとしてお伝えしたいと思います。
- ひとりとの初対面
- ① 自己開示
自己開示は、自分自身の情報をありのままに伝えることです。
自身の職業や出身地、家族構成などの個人的な「情報」を開示したり、その時の自分の気持ちや考え方などの「感情」を包み隠さず伝えたりすることは有効です。
相手に共感や理解をしてもらえると、自信を持つことができます。
情報や感情の自己開示はコミュニケーションの第一歩です。自己開示を受けると、「お返しをしなければいけない」という気持ちになります。お互いに自己開示をしあうことで信頼関係が築きやすくなります。
- ② 傾聴
「傾聴」とは相手を理解しようとする“聴き方”です。
たとえ相手の考え方や行動が容認できない場合でも無条件にそのまま受け入れること、相手の立場を想像し、あたかも自分自身のもののように感じとることを意識します。
こうした“聴き方”が伝わると、自分を理解してくれる存在を感じ、安心感を持ってもらえます。
- ③ 関係性の見直し
初対面ではない場合、それまでの関係性が影響することがあります。
「この人苦手だ」「この人が一緒なんだ、良かった」「この人のこと知っている(知っているだけ)」など、既に築かれている関係性に基づいて接し方が決まったりします。
しかし、知った人たちの中でも、つながりなおすことも必要です。これまでの関係は、立場が変われば新しい関係になります。改めて仕事に対する思いなどを話し合ってみてはいかがでしょうか?
- ④ 対立構造(TOCクラウド)
今回のコンサルティングでは、先方は「プロジェクトマネジメント」などを導入しなくてもこれまでだってうまくできていると考え、プロジェクトマネジメント導入を促すことを目的としているコンサルタントの私とは考え方が対立していました。
こういう場合は対立構造を明確にして解決方法を見つける「TOCクラウド(エリヤフ・ゴールドラット)」を用います。これは、そもそも対立構造に見える状況でも実は両立可能な部分があり、そこを起点に両者で同じ目的を導き出すことができるというものです。これにより、プロジェクトマネジメントの導入ということでなく、「このプロジェクトを成功させたい!」という共通目的を導き出しました。
- ⑤ アサーティブ・コミュニケーション
自分の気持ちや意見を、相手の気持ちも尊重しながら、率直に表現すことが、アサーティブ・コミュニケーションです。
①誠実に、②率直に、③対等に、④自己責任で、これらがアサーティブであることの「4つの柱」と言います。
- ⑥ 対話の場の提供
対話(ダイアローグ)とは、向かい合って互いの人格を認め合い、共通の現状認識を持って、お互いに納得のいく結論を導き出すことです。対話では、正しい唯一の答えは無いことを前提に、共通の理解を目指すことや相手を理解しようとすることが必要です。
対話の場を作るにあたって、きっかけは新しいメンバーの加入やマイルストーンの達成など、どんなことでも構いません。対話の場は、メンバーそれぞれの想いを聴ける場にすることが大切です。
- ⑦ 相手に合わせたコミュニケーション
ソーシャルスタイル理論(デビッド・メリル&ロジャー・レイド)にて、自分のコミュニケーションスタイルを知ると共に、相手のコミュニケーションスタイルを観察します。そのうえで、相手に合わせたコミュニケーションをしてみて、適宜修正します。
なお、人の言動や行動は、その人の性格だけでは決まらないという事を知っておくことも大切です。
- ⑧ 人との向き合い方
タイプの違う人であっても、感謝されたり褒められればうれしいと感じるのはおおむね共通しています。むやみやたらと褒めるのは避ける必要がありますが、感謝の気持ちやプラスのフィードバックをきちんと言葉にして伝えましょう。
出会いを楽しみましょう。
苦手なタイプの人と向き合う場合は無理する必要はありません。相性が良い人に頼ってみるなど他の人を活用しましょう。
もし、何をやっても効果がない気がしたときは、「風が吹けば桶屋が儲かる」と信じましょう。
- ⑨ 会議の場で意識したいこと
話しやすい環境を作りましょう。会議の冒頭でミニアイスブレイクをやり続けた結果、やらないと違和感を感じるようになったと言われました。
ゴールまでのミッション、地図を描いて毎回確認しましょう。チームビジョンを毎週読み上げるという取り組みは効果的でした。
正しい解釈かを確認し合い、その場で記録しましょう。新人や専門外の人に議事録やメモを記録してもらうと、暗黙の了解を認める雰囲気がなくなり、あいまいさが回避できるようになります。
発言機会が特定の人にだけ偏らないようにすること、また、グループシンクやアンカーリングに気を付けることも必要です。
- まとめ
プロジェクトは一人ではできません。
ひとりひとりの出会いを大切にして、信頼関係を築いていって、チームの力を高めて成功に導いていけたらと思います。
~筆者所感~
今回の講演では、講師のコンサルタントにおける体験談をもとにした貴重なヒントをたくさんいただきました。信頼関係がしっかりしたチームがうまく機能することはもちろん、そうしたチーム作りには、まずはひとりとひとりとの信頼構築からはじめるということが欠かせないことを理解できました。今後の自分の業務でも生かせるヒントをいただけたと感じます。
例会という機会を通じて貴重なお話ししていただけたことに、心より感謝を申し上げます。
ご講演の資料は協会ホームページの「ジャーナルPMAJライブラリ」の月例会開催資料に、発表資料をアップロードしていますので個人会員の方はご参照いただければと思います。
なお、我々と共に部会運営メンバーとなるKP(キーパーソン)を募集しています。ご興味をお持ちの方は、日本プロジェクトマネジメント協会までご連絡下さい。
以上
|