|
「第280回例会」報告
枝窪 肇 : 2月号
【データ】
| 開催日時: |
2022年11月25日(金) 19:00~20:30 |
| テーマ: |
リスクマネジメントの新たな潮流
~「リスクアペタイト思考」の導入~ |
| 講師: |
坂井 剛太郎 氏/株式会社竹中工務店 営業本部(大阪)専門役 |
日頃、プロジェクトマネジメントの実践、研究、検証などに携わっておられる皆様、いかがお過ごしでしょうか。遅くなってしまいましたが、11月に開催された第280回例会についてレポートいたします。
【第280回例会 報告】
~はじめに~
私(筆者)は品質保証の業務に従事しているので、リスクマネジメントについては日ごろから多くの部署にその実施を依頼しているのですが、恥ずかしながら「リスクアペタイト」という言葉を聞いたことがありませんでした。
今回のご講演では、そうした「リスクアペタイト」について、その概念や出現の背景などを、従前のリスクマネジメントとの比較も交えながらお話しいただきました。
~講演概要~
1.リスクマネジメントのおさらい
- ◆ リスクマネジメントの原点は保険
リスクマネジメントの原点は保険である。
ロイズ(Lloyd's)という保険会社の名前を聞いたことがあると思うが、ロイズとはもともとコーヒーショップの名前である。中世、港にあったこのコーヒーショップに船主が集い、海賊や台風の情報を交換する中で、皆で供託金のようなものを集めて被った被害をカバーする仕組みを作ったのが始まりで、これが海上保険の原点と言われている。その後次第に、火災保険、生命保険、疾病傷害保険や自動車保険といった保険商品へと展開されてきた。
その後も新たなリスクが顕在化する度、保険証券の条件変更とコロナ保険など新タイプの保険商品が次々に出て対応している。
- ◆ 「リスク」の基本的構成要素
リスクによって損害・影響を受ける対象をエクスポージャーという。
例えばバナナの皮が落ちていて、急いでいたためその皮を踏んで滑ってしまった。それによって衣服が汚れ、クリーニング費用が発生したとする。この例ではバナナの皮がハザード(危険な状態)、急いでいて皮を踏んだのがペリル(損失の原因)、ハザード×ペリルの同時発生による影響度が衣服の汚れであり、二次的に発生する影響であるクリーニング費用が損害、衣服がエクスポージャーである。
「リスク」は顕在化可能性×影響度として概念的に表される。
- ◆ リスクへの対応策
リスクへの対応策には、直接対応する「リスクコントロール」と、保険やリスクマネー計上など原価管理上の対応を行う「リスクファイナンス」の2つに分類される。
- ◆ リスク抽出
企業リスクを考えるとき、エクスポージャーとして『有形経営資源』の「ヒト」「モノ」「カネ」に『無形経営資源』の「情報」「チエ」「ワザ」を加えた6つの分類を用いる。
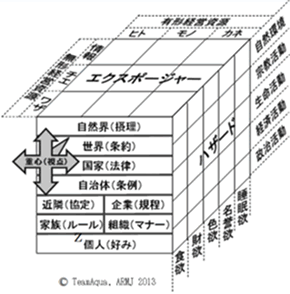 エクスポージャーに対するハザードの誘因要素として、「外的誘因要素」と「内的誘因要素」を考える。「外的誘因要素」は事前環境、宗教活動、政治活動、経済活動、生命活動の5要素で、「内的誘因要素」は五欲(財欲、色欲、飲食欲、名誉欲、睡眠欲)である。
エクスポージャーに対するハザードの誘因要素として、「外的誘因要素」と「内的誘因要素」を考える。「外的誘因要素」は事前環境、宗教活動、政治活動、経済活動、生命活動の5要素で、「内的誘因要素」は五欲(財欲、色欲、飲食欲、名誉欲、睡眠欲)である。
また、満遍なくリスクを抽出するには、その視点を広げるために、いくつかのプラットフォームを用意している。エクスポージャーに対するプラットフォーム領域間のハザード誘因要素の差異がリスク顕在化に大きく影響すると考えられる。
これを踏まえたリスク抽出支援ツールが「リスク特定キュービックモデル」である。
2.リスクアペタイトの概念
- ◆ リスクアペタイトとリスクトレランス
リスクアペタイトの概念を語るうえで大事な2つのキーワードについて、その定義を明確にする。
リスクアペタイトとは、想定されるリスクと期待するリターンの関係を踏まえた、「どのような」「どれくらい」のリスクテイクを行うかについての判断・方針である。
リスクトレランスとは、組織が許容可能なリスクの範囲・量(の上限)である。
- ◆ 一般事業会社における方針展開プロセス
企業としての「会社方針」が作られ、それが支店、部門、個人へと順次展開される。このとき、上位から下位に向けて、方針の方向性(≒リスクアペタイト)は変わってはならない。
一方で各階層(会社、支店、部門、個人)では方針に基づいて具体的な方策が練られるが、各階層・組織においては、内部・外部制約条件が異なることから具体的方策やその管理値(≒リスクトレランス)は異なるものになる。
このことから、各階層における主体組織の「やりたいこと」「できること」「やっていることの継続」等が組織全体のリワード獲得に負の影響を与えていないかの検証が必要になる。
3.「リスクアペタイト」出現の背景
- ◆ 企業を取り巻く環境変化
かつては経済追求型が主流だった企業活動であるが、環境問題や社会問題による影響が大きくなるにつれ、SRIやCSRなど企業に求められる責任が変わってきた。さらに、国連主導の持続可能性に関する施策(COP、 SDGs、 UNPRI等)も加わり、市場の上場基準もCGC(コーポレート・ガバナンス・コード)の全原則遵守が求められるようになるなど変化した。
企業の存在目的も「株主の利益のために存在する」から「全てのステークホルダーに対するコミットメントを企業の存在目的(パーパス)とする」に変化し、社会全体の価値向上を含めることが必要になった。
投資家も、ESG経営を行わない企業への投資を行わないようになってきている。
4.「リスクアペタイト思考」のERMへの導入
- ◆ 日本企業におけるパーパス浸透のための方策
日本企業においては、従業員にパーパスを如何に浸透させるかは重要な課題である。
日本ではTQM(Total Quality Management)の考え方は広く浸透しているが、TQMの特徴は経営層による経営戦略・方針のブレイクダウンと具体的な目標との同期であり、これがパーパス浸透に活用可能である。
- ◆ The Score Frameworkの活用
米英の学識団体等によるパートナーシップ「EPI」が発表した、パーパス導入のための実践的なフレームワーク「The Score Framework」は、日本企業のパーパス浸透のためのフレームワークとして展開しやすいと考える。「The Score Framework」は、Simple、Connect、 Own、 Reward、 Exemplifyで構成される。日本企業でパーパスを浸透させるためのフレームワークの例としては、パーパスをSimpleな表現とし、上位から下位の組織へ展開される方針は階層間でConnectされている。各組織/個人へのパーパスの浸透度の測定(Reward)を行い、経営者感覚(Own)の醸成と組織メンバーのアイデンティティ確立を進める(Exemplify)、といったものとなる。
5.まとめ
- ◆ パーパス×リスクアペタイトフレームワーク活用
シンプルに、利益=売上高-コストと考えたとき、従前の企業活動と求められている企業活動とを比較すると、ESG・SDGsの視点を考慮したコストは増加する方向性を持つため、これまでと同等の利益を得るためには売上高を上げなくてはならない。
そのためには新市場の開拓や、新商品・サービスの開発などの活動行うことが求められるようになる。現市場や現商品・サービスの近隣エリアでの拡大においては、これまでの「リスクマネジメント」(リスクコントロール・リスクファイナンス)の活用で対応可能だったのに対し、新規事業などの方針のもとでは、「リスクアペタイト」(リスクアペタイトの設定・リスクトレランスの設定)が必要になってくる。
リスクアペタイト/リスクトレランスの導入においては、パーパス、策定プロセス、経営資源、アカウンタビリティといった視点が重要となる。
パーパスとの連動を前提に、進むべき方向性(リスクアペタイト)を見極め、推進力の限界値であるリスクトレランスを判断する必要がある。
パーパス経営を支えるのが、リスクアペタイトフレームワークを活用した戦略的ERMである。
~筆者所感~
今回の講演では、リスクへの対応において、「リスク特定キュービックモデル」を用いたリスク抽出や、従前のリスクマネジメントと比較する中でこの時代に求められる「リスクアペタイト思考」を解説頂き、大変参考になりました。今後の自分の業務への大いなるヒントになったと感じます。
例会という機会を通じて貴重なお話ししていただけたことに、心より感謝を申し上げます。
ご講演の資料は協会ホームページの「ジャーナルPMAJライブラリ」の月例会開催資料に、発表資料をアップロードしていますので個人会員の方はご参照いただければと思います。
なお、我々と共に部会運営メンバーとなるKP(キーパーソン)を募集しています。ご興味をお持ちの方は、日本プロジェクトマネジメント協会までご連絡下さい。
以上
|
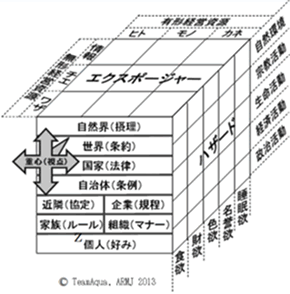 エクスポージャーに対するハザードの誘因要素として、「外的誘因要素」と「内的誘因要素」を考える。「外的誘因要素」は事前環境、宗教活動、政治活動、経済活動、生命活動の5要素で、「内的誘因要素」は五欲(財欲、色欲、飲食欲、名誉欲、睡眠欲)である。
エクスポージャーに対するハザードの誘因要素として、「外的誘因要素」と「内的誘因要素」を考える。「外的誘因要素」は事前環境、宗教活動、政治活動、経済活動、生命活動の5要素で、「内的誘因要素」は五欲(財欲、色欲、飲食欲、名誉欲、睡眠欲)である。