|
「第279回例会」報告 枝窪 肇 : 11月号
【データ】
日頃、プロジェクトマネジメントの実践、研究、検証などに携わっておられる皆様、いかがお過ごしでしょうか。今回は、9月に開催された第279回例会についてレポートいたします。 【第279回例会 報告】 ~はじめに~ 講師の阿部様は品質マネジメントシステムの構築・維持の業務に従事し、マニュアル通りに作業が行なわれているか、そのうえで、品質が保てているかを、確認されていました。また、監査などでは如何にして現場が自らの意思で改善に取り組むことを促せるか、といった課題に向き合われていました。 今回のご講演では、そうした課題の解決に役立つ、マニュアルの内容がうまく伝わらない原因や、わかりやすいマニュアルの作り方、わかりやすく相手に物事を伝える方法を、ドラッカーのコミュニケーションについての記述を元にお話しいただきました。 ~講演概要~ ◎コミュニケーションとは ウィキペディアでは、社会生活を営む人間の間で行われる知覚や感情、思考の伝達。とある。言語だけではなく、目と目で通じ合うといったものもコミュニケーションである。語源は「疎通を良くする」ということで、お互いに通じ合って、表面的ではなくお互いの内面に働きかけるという意味がある。 ドラッカーの著書の「マネジメント」では、コミュニケーションについて
情報自体はコミュニケーションではないが、受け手の知覚を通すことでこちらの情報が受け手に要求として伝わり、自分の知覚を通すことで受け手の期待を知ることができる。 ◎コミュニケーションを成立させるのは受け手 ソクラテスは「大工と話すときは大工の言葉を使え」と、孔子は「辞は達するのみ」と言った。これらは共に受け手に伝わることが大事で、受け手に伝わらなければ発信したことにならないということを意味している。 孔子は、弟子から、生きていく上で、一番大切なことは何かと問われたときに「恕(じょ)」であると答えた。「恕」は思いやりという意味で、その字のとおり、相手の「心の如く」なって相手の立場・気持ちを自分の事のように考えるということである。 ◎受け手の期待を知る 受け手は自らが求めるものを提供してもらえると期待するので、期待と無関係なことを伝える場合はそのことを強調する必要がある。受け手が期待しているものを知ることなくコミュニケーションを行うことはできない。 ◎マニュアルはコミュニケーションの手段 コミュニケーションは、我われ組織の中の一人から、我われ組織の中の別の誰かに伝達することであり、受け手に行動することを要求することである。その意味から社内手順書(マニュアル)はコミュニケーションのツールであると言える。 現場をその気にさせる!マニュアル人間を作らないマニュアル作りに必要なことは、①当事者意識、②使用者目線、③目的・理由の明確化である。 組織の思想・事業継承、改善のためのマニュア作成に必要なことは、④はじめにメンテナンスすることを考えておく、⑤共通ルールはまとめる、⑥定期的に現場を巻き込んで見直し、改善する、⑦組織のミッションを明文化しそれと矛盾しない内容・体系とすることが大切である。 ◎集合的無意識を意識する 人には普遍な共通イメージがあり、これを集合的無意識という。「人類共通」の集合的(普遍的)無意識は、国や民族を超えて人類全体に共通して存在する。 この集合的無意識の中の共通イメージを利用したデザインは、時に言葉の説明を不要にする。ISOマークの多くはこの共通のイメージを利用している。JISの温泉マークは、他国の人たちには温かい料理に見える、すなわちそれが共通のイメージなのだが、温泉として慣れ親しんだ日本人にはもはや温かい料理には見えない。このように慣れが共通イメージをかき消すこともある。システムもそうだが、一度慣れると、途中変更が困難になることがあるので、最初にいかに共通イメージに合ったものにするかが肝要である。 ◎経験の共有が完全なコミュニケーション 中島みゆき氏とプロデューサーの瀬尾一三氏は30年以上ともに仕事をし、経験を共有した。その結果、二人は、ほとんど言葉による説明や要求なしに完全な仕事をすることができている。長年連れ添った夫婦でも同様のことが見られる。つまり、コミュニケーションの成立には経験の共有が不可欠であり、経験を共有することで完全なコミュニケーションが実現できる。 リモート全盛の時代ではあるが、イーロン・マスク氏はテスラ社員に「リモート勤務を認めない!」と通知した。背景に経験の共有により社内コミュニケーションを重視する氏の考え方が見て取れる。 経験の共有の今昔ということでは、昔は情報量は少ないものの、目や耳からの情報で、誰が何をしているかを把握することができた。その後情報量が増えてPCでの業務が普及する中で、他人が何をやっているかわかりづらくなり、経験を共有しにくくなった。リモート全盛のニューノーマルの現在は、情報は十分に収集できるが、場の経験の共有が難しくなってしまっている。情報が多くなるほど、コミュニケーション・ギャップは縮小するどころかかえって拡大する。 メラビアンの法則では、コミュニケーションにおいて言語・聴覚・視覚から受け取る情報がそれぞれ異なった際、人は言語を7%、聴覚を38%、視覚を55%の割合で重視するとされている。つまり、場を共有していれば、視覚、聴覚からの印象が言語コミュニケーションを補完してくれるということである。ただし「話の内容」を疎かにして良いという意味では決してないので注意してほしい。 「話の内容」をメールやチャットだけで伝えると、時に疑心暗鬼になったり、感情的な誤解が生じやすくなり、その結果として忖度や保身が生じる。経験を共有しにくいニューノーマル時代のコミュニケーションにおいては特に、忖度や保身ではなく目標・成果・貢献に焦点を合わせることが重要である。ドラッカーも成果をもたらす関係であるならば失礼な言葉があっても人間関係を壊すことはないとしている。 ◎見方の違いを知ること自体がコミュニケーション~異なる意見こそ大切 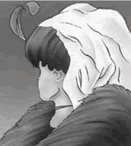 有名な左の絵がある。大抵の人は貴婦人に見えるのだが、中には老婆に見える人もいる。老婆に見えると言われたときに、そんなはずはないと相手を全否定してしまうとこの絵の真実は見えてこない。明らかに違ったことを言っている人は、自分とは違う現実を見て、違う問題に気付いているに違いないと考えるべきである。違う意見があることを知ることが大切である。
有名な左の絵がある。大抵の人は貴婦人に見えるのだが、中には老婆に見える人もいる。老婆に見えると言われたときに、そんなはずはないと相手を全否定してしまうとこの絵の真実は見えてこない。明らかに違ったことを言っている人は、自分とは違う現実を見て、違う問題に気付いているに違いないと考えるべきである。違う意見があることを知ることが大切である。ここに2つの質問を提起する。 Q: 世の中に”真理”はあるか? Q: その”真理”を、人はつかめるか? ドラッカーは”真理”はあるが、人は”真理”をつかめないと言う。 ところが、時に自分は”真理”をつかんだという者がでてくる。いわゆる絶対主義者であり、”真理”をつかんだ自分がすべきことは、①まず、言うことをきかせる、②聞かない者は救いようがない。なぜなら真理がわからないから、③よって真理の実現のために粛清する。④これが私の義務であり正義であると考える。 絶対に正しいという人がいたら、その人は間違えていると考えるべきであろう。 ◎忖度は最悪のコミュニケーション 群盲象を撫でるという諺がある。目の見えない人たちが1頭の象を触っている様子を表しているのだが、耳を触っている人はパタパタして広いもの、牙に触っている人はとがっていて危ないものなど、それぞれがそれぞれに意見を言う。もしも牙に触っている人が象はとがっていて危ないものであるという事だけを信じてしまうと全体像(真実)が見えなくなる。逆に言えば、全会一致の状況とは、全員が牙にしか触っていないということであると考える。こういう場合には意図的に意見の不一致を作り上げることによって間違っている意見や不完全な意見によって騙されることを防ぐ。意見の不一致の原因を突き止めることで象の全体像が分かってくるのである。 象の鼻を触っている社長が、象は長いホースだと言った際に、違うと思っても意見を言わずに忖度してしまうようなことがあるかもしれないが、人の気持ちを気にしなければならない状況は最悪の人間関係であるとドラッカーは言った。相手の気持ちを気にして、押し黙るのではなく、意見の違いを認め合う組織にならなければならない。忖度せず、知らないことを知ることが、創造的生産的なコミュニケーションを生む。 ◎人生の方程式 一番大切なものは”よき考え” 熱意や能力にはマイナスは無いが、考え方にはマイナスがある。 考え方がマイナスの例は、消費者をだます詐欺師である。災害、新制度の導入、疫病などの社会不安、結婚・就職などの個人の不安を適時利用して、人をだますのである。頭が良くて熱意もあるが、考え方はマイナスであり、最終的には良い結果をもたらさない。 ここまでコミュニケーションの話をしてきたが、その前提には”よき考え”がある。”よき考え”から発せられた言葉であれば、誤解があっても何とかなる。ただ、今はリモート環境で誤解を埋めることが難しくなっているので、組織のミッションのような共通の目標を明確にしなければならないと思う。 孔子の言葉に、 これを知る者はこれを好む者に如かず。これを好む者はこれを楽しむ者に如かず。 とある。日本は現在、人口激減や急激な円安など、ある意味で未曽有の危機にあると言えるが、ドラッカーは、日本は危機の時こそ強いと言っている。 同じことをやる場合、ただやるのと、好きでやるのと、楽しくやるのでは、楽しくやる方がより積極的になって良い考えも浮かんでくる。危機さえも楽しむ気持ちで立ち向かい、日本を浮上させることができればと考える。 ~筆者所感~ 今回の講演では、講師のこれまでの経験の中から、コミュニケーションがうまくいかなかったときに、どのようにしてうまくいくようにできたかなどを、多くの事例とともにご紹介いただきました。実際の体験を通じた内容だったので、非常に分かり易い内容でした。また、それらが、ドラッカーのコミュニケーションとどのような関係性があるかを紐づけてくださることで、大変参考になるお話となりました。 例会という機会を通じて貴重な体験をご紹介いただけたことに、心より感謝を申し上げます。 ご講演の資料は協会ホームページの「ジャーナルPMAJライブラリ」の月例会開催資料に、発表資料をアップロードしていますので個人会員の方はご参照いただければと思います。 なお、我々と共に部会運営メンバーとなるKP(キーパーソン)を募集しています。ご興味をお持ちの方は、日本プロジェクトマネジメント協会までご連絡下さい。 以上
|