|
「第275回例会」報告 原 宣男 : 9月号
【データ】
Ⅰ.はじめに 成功事例に比べ失敗事例のほうが遥かに多いと思われるプロジェクトマネジメントの世界で、先達が苦労して体験・体得した知識やノウハウ、経験等を物語形式で記録し、それを元に成功や失敗を疑似体験させることにより今後のプロジェクト運営を成功に導く「ものがたり継承法」は、プロジェクトに携わり苦労されている方々にとっては、とても興味を惹かれる手法だと思います。 今回紹介された「ものがたり継承法」は、2012年にFMCS社(当時あった富士通(株)のSE会社)の社長であった宮田一雄氏が社内で立ち上げたナレッジ継承活動の成果物である「FMCSものがたり集」と、その後2018年から富士通(株)社内で展開された「ものがたり継承法」の成果物である「DX実践記」をもとに、講師である吉野均氏がそれに磨きをかけたもので、最近発足した「PMノウハウ継承研究会SIG」で研究が始められ、また5月にPMAJ特別講座にも組み込まれています。 本日は講師より、その「ものがたり継承法」について説明いただきましたので、その概要を以下に紹介いたします。 尚、紙面の都合で内容をかなり絞ってのご紹介となっておりますこと、ご了解願います。 Ⅱ.講演概要 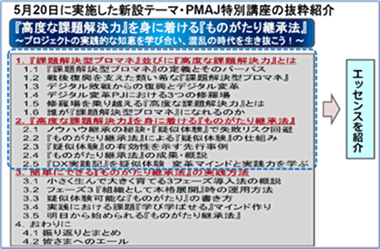 当講演は5月20日に実施した新設テーマPMAJ特別講座の抜粋を紹介するものである。1章で課題解決型プロマネとは何かを定義し、プロフェッショナルに必要な高度な課題解決力とは何かをわかりやすく説明している。2章では高度な課題解決力を大失敗のリスクを犯さずに身につける方法として「ものがたり継承法」を提案している。3章でその「ものがたり継承法」を簡単に実践できる方法を提示している。当講演はこのうちの1章と2章のエッセンスを紹介する。
当講演は5月20日に実施した新設テーマPMAJ特別講座の抜粋を紹介するものである。1章で課題解決型プロマネとは何かを定義し、プロフェッショナルに必要な高度な課題解決力とは何かをわかりやすく説明している。2章では高度な課題解決力を大失敗のリスクを犯さずに身につける方法として「ものがたり継承法」を提案している。3章でその「ものがたり継承法」を簡単に実践できる方法を提示している。当講演はこのうちの1章と2章のエッセンスを紹介する。1.「課題解決型プロマネ」並びに「高度な課題解決力」とは 1.1 「課題解決型プロマネ」の定義とそのパーパス 課題解決型プロマネは、組織の課題を解決するため組織のリーダーとともにプロジェクト目標を定め、必要なステークホルダーやプロジェクトメンバーを巻き込み、解決すべき課題を抽出し、課題解決を繰り返し、時にはプロジェクト目標を臨機応変に見直し、プロジェクトを組織の課題解決に導くプロマネである。これを踏まえ課題解決型プロマネは類まれな課題解決力を持ち高度な組織の課題解決をリードできるプロマネと定義する。プロマネのパーパス、存在意義はプロジェクトマネジメント力で組織の課題解決に貢献することにあると考える。 1.2 戦後復興を支えた類い希な「課題解決型プロマネ」 プロジェクトX挑戦者たち第1回は、「巨大台風から日本を守れ、富士山頂・男達は命をかけた」であるが、このプロジェクトの概要とそこに登場する課題解決型プロマネを紹介している。このプロジェクトの成功に貢献したプロフェッショナルな挑戦者たちのうち、総責任者である気象庁の藤原課長が、まさに課題解決型プロマネの典型と言える。 プロジェクトXでは語られていない藤原課長の苦悩と苦闘は、新田次郎の著書「富士山頂」に残されている。「富士山頂」は藤原課長の経験を忠実に再現した物語であり、藤原課長が類まれな課題解決力の持ち主であったことを伝えている。 1.3 デジタル敗戦からの復興とデジタル変革 (目次のみの紹介の為、内容省略) 1.4 デジタル変革プロジェクトにおける3つの修羅場 DXプロジェクトには、まずコンセプト検証とシステム実現フェーズの間に「魔の川」がある。アイデア発掘と試作の試行錯誤を繰り返し、「魔の川」を渡りきれず、システム実現フェーズを開始できない修羅場である。次に、システム実現フェーズとシステム運用フェーズの間に「死の谷」がある。システム実現工程で試行錯誤を繰り返し、システム運用フェーズを開始できない修羅場である。さらにシステム運用を開始した後に「ダーウィンの海」がある。システム運用のトラブルやもともとのコンセプトが市場に受け入れられず事業拡大を図れない修羅場である。場合によっては「ダーウィンの海」で自然淘汰され、市場から撤退となる。つまり課題解決型プロマネには、この三つの修羅場を乗り越える高度な課題解決力が必要である。 1.5 修羅場を乗り越える「高度な課題解決力」とは 修羅場を乗り越える高度な課題解決力は、一般にはPM実践力またはPM実践知と呼ばれるものである。このPM実践力を「課題志向性」と「課題解決力」の二つに分けて定義する。「課題志向性」は、⓪強い目的意識と修羅場でも決してくじけない精神力であり、「課題解決力」は、①課題を発見する力、②冷静に状況を把握する力、③複数の打開策をひねり出す力、④最善の策を決断する力、⑤成功に導くリーダーシップ力、そして⑥状況変化への柔軟な対応力の6つの力である。PM実践力はこの「課題志向性」と6つの「課題解決力」が掛け合わされ機能していると定義する。 課題解決プロセスは、課題を発見、予備調査、複数の仮説を立案、比較評価してひとつを選択、仮説の実行、結果評価と対応、この6つのフェーズをOKとなるまで繰り返すプロセスである。嵐に遭遇した船長は、外部からの救援は間に合わない、船の設備や燃料船員といった限られたリソースを使って絶体絶命のピンチをどう乗り切ればよいか、安全確実に乗客を目的地に運ぶためにはどうすれば良いか、という絶体絶命の危機に立たされたプロマネそのものである。嵐に遭遇した船長の最終ゴールは、安全確実に目的地に乗客を運ぶということ。 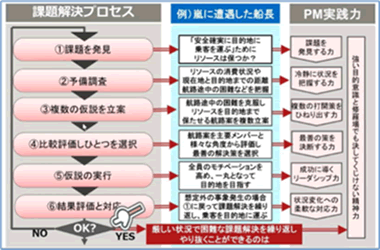 そのため嵐に遭遇した船長が最初に発見した課題は何だったか。それは安全確実に目的地にお客を運ぶためにリソースは持つかということである。これはPM実践力の①課題を発見する力。次に「予備調査」ではリソースの消費状況や現在地と目的地までの距離、航路途中の困難などを把握する。これはまさに②冷静に状況を把握する力である。次の「複数の仮説を立案」する。
そのため嵐に遭遇した船長が最初に発見した課題は何だったか。それは安全確実に目的地にお客を運ぶためにリソースは持つかということである。これはPM実践力の①課題を発見する力。次に「予備調査」ではリソースの消費状況や現在地と目的地までの距離、航路途中の困難などを把握する。これはまさに②冷静に状況を把握する力である。次の「複数の仮説を立案」する。ここでは航路途中の困難を克服し、リソースを目的地まで持たせる航路案を複数立案する。これが③複数の打開策をひねり出す力。そして「比較評価しひとつを選択」では、航路案を主要メンバーと様々な角度から評価し、最善の解決策を選択する。これが④最善の策を決断する力。そして「仮説の実行」では全員のモチベーションを高め、一丸となって目的地を目指す。これはまさに人を巻き込む力で、⑤成功に導くリーダーシップ力に対応付けられる。そして「結果評価と対応」では想定外の事象発生の場合はじめに戻って課題解決を繰り返し、乗客を目的地に運ぶこと、これは⑥状況変化への柔軟な対応力である。そして厳しい状況で困難な課題を繰り返しやり抜くことができるのは、⓪強い目的意識と修羅場でも決してくじけない精神力があるからである。 1.6 誰が「課題解決型プロマネ」になれるのか DXプロジェクトに参加する様々なプロフェッショナルのうちで、誰が課題解決型プロマネになれるか? 講師は、プロの誰もが課題解決型プロマネの候補と考えている。プロなら類まれなとまではいかないが、課題解決力を持っているからである。その中でプロマネが経営のプロに次いで課題解決型プロマネに変われる可能性が高いと期待している。 なぜプロマネが課題解決型プロマネに変われるのか? プロマネはプロフェッショナルの力を集結・リードする経験をシステムフェーズで積んでいるからである。主体的に関与するフレーズを広げていくことで課題解決型プロマネの一歩を踏み出すことができる。 誰が課題解決型プロマネになれるか? もう一歩踏み込んで考えてみる。混乱した時代にあってDXプロジェクトに参加するすべてのプロは、より高度な課題解決力を持つ必要がある。「全体の善」の実現に向けて各専門分野の課題解決に自立して取り組む必要があるからである。そのうちの類まれな課題解決力の持ち主が課題解決型プロマネになるというのが現実解ではないだろうか。 2.「高度な課題解決力」を身に着ける「ものがたり継承法」 2.1 ノウハウ継承の秘訣・「疑似体験」で失敗リスク回避 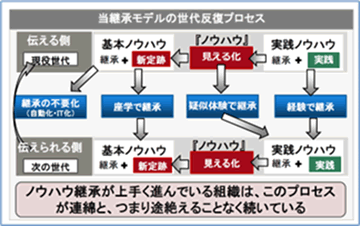 修羅場を乗り越える高度な課題解決力・PM実践力は、継承困難である。属人的かつ一過性のもので組織の知とならず、先達の引退とともに消え去っていく。そのため同じような失敗を繰り返す事例が見受けられる。各組織ではこの課題解決のために様々な方法によりPMノウハウ継承に取り組んでいるが、うまく継承できていない。そこでノウハウ継承の成功事例を分析し、その秘訣を抽出、モデル化した。それを世代反復型ノウハウ継承モデルと呼んでいる。
修羅場を乗り越える高度な課題解決力・PM実践力は、継承困難である。属人的かつ一過性のもので組織の知とならず、先達の引退とともに消え去っていく。そのため同じような失敗を繰り返す事例が見受けられる。各組織ではこの課題解決のために様々な方法によりPMノウハウ継承に取り組んでいるが、うまく継承できていない。そこでノウハウ継承の成功事例を分析し、その秘訣を抽出、モデル化した。それを世代反復型ノウハウ継承モデルと呼んでいる。PM実践力の継承における最大の課題は、PMスキル熟達の過程に存在する「経験で継承」のリスク。「経験で継承」のリスクが顕在化すれば大惨事となってしまう。PM実践力が継承困難とすれば、課題解決力を高めるにはどうすればいいか? そこで役立つのが「ものがたり継承法」である。経験のない範囲の課題解決を物語で擬似体験することにより、大失敗のリスクを犯さずに課題解決力を高めることができるのである。 2.2 「ものがたり継承法」による「疑似体験」の仕組み 「ものがたり」とはPMノウハウ継承に役立てる目的を持ってプロジェクトの実践を物語形式で見える化した経験の記録である。「ものがたり継承法」とはプロジェクトで発揮されたPM実践知を自らの経験を振り返ることで自ら学び、経験の記録として「ものがたり」に見える化し、その「ものがたり」を疑似体験させることにより次世代に学ばせる継承法である。 「ものがたり継承法」の狙いは、組織の価値観やノウハウを継承しつつ新たな価値創造に果敢に挑戦するマインドと実践力を持つ人材を育成する事にある。 「ものがたり」には遭遇した課題とその解決策だけでなく解決に至るプロセスを克明に記載する。どんな価値の実現を目指し、途中どういう状況に陥って何を考え、何に悩み、どんな苦労をして周りを巻き込み、解決策発見の試行錯誤を繰り返し、どうやって価値を実現できたか。プロジェクトの成否を分けた課題解決プロセスで発揮されたPM実践力を見える化している。「ものがたり」執筆者は執筆を通して、プロジェクトの成否を分けた課題に着目し、その課題解決に至るまでの経緯を生々しく再現するが、そのためには経験を省察、つまり深く考える必要がある。これによって経験が再現可能な実践力になる。一方の「ものがたり」読者は、「ものがたり」を熟読することでプロジェクトの成否を分けた課題解決プロセスを疑似体験し、プロジェクト固有の課題を解決できるPM実践力を鍛えることができる。 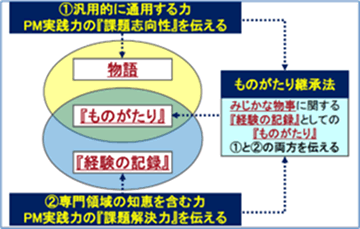 この仕組みにより修羅場の課題解決プロセスを疑似体験し、大失敗のリスクなしで課題解決力を高めることができる。
この仕組みにより修羅場の課題解決プロセスを疑似体験し、大失敗のリスクなしで課題解決力を高めることができる。「ものがたり」疑似体験には二つの側面がある。①汎用的に通用する力を伝えるには、物語が適しており、②専門領域の知恵を含む力を伝えるには経験の記録が適している。しかし物語からは専門領域の知恵は学べず、経験の記録は専門領域の知識がないと読めない。しかし「ものがたり継承法」は、身近な物事に関する経験の記録としての「ものがたり」であるから、この①と②の両方を伝えることができる。 2.3 「疑似体験」の有効性を示す先行事例 疑似体験の有効性を示すために、先行事例①で課題志向性を物語で伝えることに成功した事例を、先行事例②では、この専門領域の知恵を含む力を経験の記録で伝えることに成功した事例を紹介する。 先行事例①は、先ほど課題解決型プロマネの典型としたプロジェクトX挑戦者たちの藤原課長の物語である。藤原課長は富士山レーダー完成の2年後に退官し、新田次郎のペンネームで夢と挑戦の物語を書き続けた。新田次郎の物語やプロジェクトXは課題解決志向に導く疑似体験ができ、新たな挑戦に勇猛果敢に挑む変革マインドを奮い立たせてくれる。 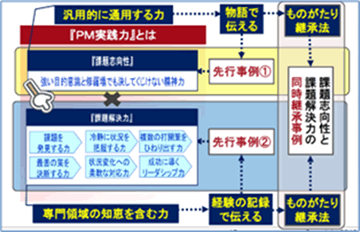 先行事例②は、新幹線新丹那トンネル開削工事、国家の大事業土木プロジェクトの事例である。この工事は昭和39年東京オリンピックに間に合わせるべく進めた東海道新幹線開業の最大の難工事と言われている。それ以前に旧丹那トンネル開削という工事があった。これはまさに水との戦いであった。工期16年、100名の犠牲者が出た。新丹那トンネル工事は、技術革新はあるが、工期は4年、前回の1/4である。
先行事例②は、新幹線新丹那トンネル開削工事、国家の大事業土木プロジェクトの事例である。この工事は昭和39年東京オリンピックに間に合わせるべく進めた東海道新幹線開業の最大の難工事と言われている。それ以前に旧丹那トンネル開削という工事があった。これはまさに水との戦いであった。工期16年、100名の犠牲者が出た。新丹那トンネル工事は、技術革新はあるが、工期は4年、前回の1/4である。その工事に臨むにあたって、現場責任者である坂本氏が準備段階で最初にしたことは、旧丹那トンネル開削工事記録を読み込んだことである。そこで出水した場所、打った対策、解決に要した期間など、全て調べ上げた。まさに経験の記録で擬似体験した。その上で存命の技術者、作業員に当時の話を聞き、過去の経験・反省を踏まえて新技術適用で引き直し、工事計画書を作成したと言われ、この事実は坂本氏が新幹線新丹那トンネル開削工事という記事で、「文芸春秋にみる昭和史」に書いているとおり、まさに経験の記録による疑似体験の成功事例といえる。 2.4 「ものがたり継承法」の成果・概説 ミッションクリティカル領域の「ものがたり集」とデジタル変革領域の「DX実践記」について紹介するが、二つの適用領域には明確な特徴の差異がある。ミッションクリティカル領域のプロジェクトはビジネス継続に必要であり、システム要件は既定、きちんと計画し、しっかり実行することが求められる。従って絶対に失敗できない。一方のデジタル変革領域のプロジェクトは、競争力を高めるのに必要である。よってシステム化要件を探索しながら、試行錯誤のリスクに挑戦しなければならない。従って時には失敗も許容される。ミッションクリティカル領域のPM像は失敗しないプロマネである。まさにドクターXの大門未知子「私失敗しないので」のプロマネ版。一方の課題解決型プロマネは、地上の星プロジェクトX挑戦者たちである。求められるPM像は異なり、鍛え方は微妙に異なっているが、「ものがたり継承法」は両領域とも有効であることが実証されている。 (「ものがたり集」についての紹介は省略) 2.5 「DX実践記」を疑似体験 変革マインドと実践力を学ぶ DX実践記の一つを取り上げて疑似体験頂く。 (紙面の関係で紹介されたDX実践記の一部のみを以下に記載) 稼働まで残り4ヶ月、プロジェクトは危機的な状況に陥る。ここに至ってもプロジェクトの方針は当初方式の継続であった。ソフト部部長は冷静に状況を分析し自問自答する。既存技術では認識性能に限界がある。多大な工数がかかる上にできたとしても拡張性は無い。一方でディープラーニングによる実現は新パッケージ適用に機能追加が必要である。残念ながら新パッケージ開発元とはまだ調整できていない。我々はディープラーニングのやり方もわからない、しかしディープラーニングには将来性発展性がある。今ディープラーニングをやらなければ富士通は生き残れない。自分のミッションにかなうディープラーニングにチャレンジしようと、技術アドバイザーという立場を越えて、プロジェクトに関わり未経験なディープラーニングにチャレンジすることを決断する。その直後12月2日プロジェクト責任者が社内会議を招集した。緊急会議で当初方式派と方式変更派に分かれ、喧々諤々の議論が交わされる。結論が見えない中で、ソフト部部長はディープラーニングについてはソフト部が責任を持って実施させて頂きますと宣言した。この宣言によって一気に会議の雰囲気が変わり、ディープラーニングへの方針変更が全員一致で決定された。この宣言はプロジェクトから与えられた役割を越え、火中の栗を拾う課題解決型プロマネの決断の言葉といえる。この後ソフト部部長は魔の川、死の谷、ダーウィンの海の障害を様々なプロフェッショナルを巻き込んで乗り越えていく。 3. 簡単にできる「ものがたり継承法」の実践方法 (目次のみの紹介の為、内容省略) 4. おわりに プロマネのパーパスは、プロジェクトマネジメント力で組織の課題解決に貢献せねばならない。そのために元々保有する課題解決力に磨きをかけ高度な課題を解決できる能力を身に着ける必要がある。それを支える意思として、課題解決型プロマネに生まれ変わるという確固たる意思が求められる。きっと成功させるという決意こそが何にもまして重要であるということを決して忘れてはならない。 Ⅲ.所感 特別講座で何時間もかけて解説される内容を、例会という時間が限られたなかでエッセンスだけご紹介いただいたので、その場ではどういう内容なのか、ぼんやりとしか把握できなかったのですが、改めて講演資料を確認すると、その重要さと大変さがわかったような気がします。 成功事例や失敗事例が記載されたものはありますが、疑似体験できるような詳しく書かれたものはそんなには無いと思いますので、今後のPMノウハウ継承研究会SIGの成果物としての「ものがたり集」に期待したいと思います。 また、「ものがたり継承法」に興味を持たれた方は、ぜひ同SIGに参加され、その研究及び成果物作成に注力して頂ければ幸いです。 「ものがたり継承法」を紹介いただいた講師と、社内展開された手法を公開していただいた関係者各位に感謝いたします。 |