| Z. |
芝さん。不幸なことに安倍総理の変事でアベノミクスの運営がどうなるか後継者の出現があるかわかりませんが、これまでのアベノミクスの構成とその戦略、戦略実施とその成果等を時系列的にお話しいただけますか。また読者にわかりやすく読んでいいただくための工夫をお願いします。
Ⅰ.【日本国の乖離する税収と歳出】図表から見たアベノミクスの解説を添付しました。
【タックス・イーター】=消えていく税金=(著者:志賀 櫻、初版2014年12月)
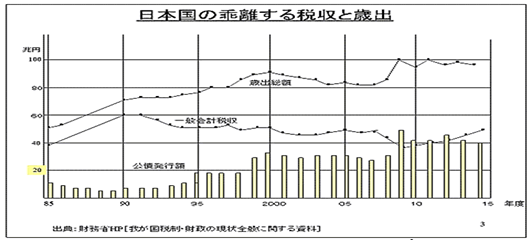
|
| 芝. |
おっしゃるとおりですね。私がこの仕事に注目したのはタックス・イーターの著者の願いに共感したからです。「著者志賀 櫻氏が冒頭に述べた言葉【国民の税金を食い荒らし、富を奪い取る者は誰だ、政治と経済に隠然たる力を及ぼし、法を逆手にとりながら、文明の対価である税を掠めてゆく。揺らぐ財政の屋台骨。国を存立の危機に追い込む悪行を見過ごしてよいのか】を追及する」。
私の願いも同じで、アベノミクスは年度ごとの決算を出す必要があると願っています。 理由は財務省がデフレのための増税を決定したからです。好景気での増税は認められますが、世界中の国はデフレ対策を講じます。昭和の大蔵省に「ミスター円」と称する榊原英資財務官が活躍していました。彼は日本が円高で行く方針を守りました。理由は日本の輸入の半分は燃料でした。燃料のすべてを海外から輸入していたので、円高が好都合でした。その他の輸入品も円高で安く買えました。輸出品は競争力を失いますが、日本からの輸出品は高精度製品がおおく、値下げなしに輸出できます。これがミスター円自慢の種でした。しかし令和では競争相手がふえており、アベノミクス製品のすべてに競争力があるわけではありません。 |
| Z. |
国民は輸入品が安くなると、得をした感じになりますがどうですか?その代り輸出業者は損をしたことになります。 |
| 芝. |
燃料輸入の多い日本では、その通りです。しかし、日本製品は円高になっても、商品の品質が高いため、高値で売れるので輸出でも収益が得られましたが、昨今の状況では商売が難しくなります。
図上・1985年以前から【大型技術開発テーマを選び、筑波地域に大型技術開発センターをつくり】この大型研究センターのための投資を推奨し、国民も財テクに応じましたが。我が国で大きな財テクをすることは初めてでした。1985年からと、1990年までの運営は大蔵省官僚の努力で大成功と思われましたが、その成功に欲が出て、1997年には山一証券の破綻によって、急遽国の調整活動によって、2005年までに復旧活動予算が決まりました。国が担う予算が200兆円になり、この金は官が使う資金であるから、民間関係の仕事はしないと財務省は日銀法を見せて強調していました。この法律は官に関係するものだけで、公共投資、国から要請以外は国債の発行を禁止しているという発言。そこでアベノミクス関連者が日銀に交渉すると、“明日おいで”という話でした。米国の事例はそのような仕事で国が面倒見ないということはあり得ないということで、有名な学者、ノーベル経済学賞者にも立ち会ってもらい、日銀も許可の範囲を広げてもおかしくないということで、認めてもらいました。
官は規則から外れたことは拒否されても構いませんが、日本では扱いませんという発想に、はずかしさを覚えました。
さらに心配な問題があります。すべてのテーマとその予算案をまとめて中間発表することです。
アベノミクスで行われることはすべて予算案ができているはずです。私の心配は国民に実施させるプロジェクトはすべて複式経理が採用されていますが、官の領域では複式で実行しないことのようです。それでは「タックス・イーター」を防ぐことは無理になります。
Ⅱ.ここで少し面白い話を聞いてください。1990年に日本は製造業で世界1になりました。うれしい話ですね。
第二次世界大戦の戦勝国ロシアの話を聞いてください。今のロシアは大変ですね。大戦終了後のソ連邦は1991年ソ連邦方式を解散し、民主的な資本主義を取り入れました。ゴルバチョフ大統領は6年で民主的資本主義体制を整えました。
- ゴルバチョフ内閣が終わり、エリチン大統領に代わると、エリチン大統領はロシアの豊富な石油資源を7つの石油財閥に分けました。経営者はいずれもユダヤ財閥でした。プーチンはユダヤ財閥が結束し、米国の石油財閥と手を結ばれるとこまると考え、ロシアの大統領選挙に立候補し、大統領になり、7つの石油財閥の縮小化を図ってきました。ところが米国のネオコン(現在の国務省主力メンバーはこのネオコンが支配しています。)が、ロシア石油財閥の筆頭企業から、自分の持ち株の50%を米財閥に譲る提案がありました。その提案を聞いてプーチン大統領は7財閥 の所有物件をすべて取り上げた。プーチン大統領はネオコンと重要な約束をしています。ウクライナにはNATOを介入させないという提案です。
それに対してネオコンとプーチン大統領の間に溝が生まれました。ウクライナの次期大統領選挙でネオコンは別人を大統領に当選させたため、プーチン大統領は、ウクライナに進軍し、クリミヤ半島を占領し、今日にいたっていますが、ロシア人にとって、クリミヤ半島はロシアの最大の要塞なのです。ロシア人にとってウクライナの要塞ではなくロシアで最大の要塞地という存在です。(注:ロシアのクリミヤ半島へのこだわりとは:ロシアという国は陸続きで、太平洋、大西洋に出る港がなく、クリミヤ半島が昔からのロシア最大の要塞でした。)
- ロシアの港1.サンクト・ペテロブルグ港からバルト海経由で大西洋
- ロシア第二の港 : 黒海に突き出たクリミヤ半島の港、黒海経由地中海→大西洋
- ロシア第三の港 : 日本海に面した「ウラジオストック港」の3港しかない。
もしあなたがプーチン大統領なら何をするか真摯に考えてみて欲しい。クリミヤ半島をウクライナの要塞にしたら、ロシア攻撃は簡単です。あなたなら何をしますか。
Ⅲ.米国の新しい要塞(地域要塞ではなく情報要塞地)
- 1995年米国はグローバリゼーション制覇のため、【インターネットなる通信網】を世界中に広げました。この通信網は世界中の国と国境という制約無しに、常時通話ができます。各国の首都に通信塔を設ければ、世界中の情報は全部集まります。米国の大勝利でした。
- 米国の次の世界制覇への道は2000年からの【IT戦力の向上:スピード、情報の質と量、掘り下げ可能な情報の質の向上】に成功し、大型コンピュータに経営の規模と正確性の向上で、それぞれの経営の質の高さを極めてきた。
- 最初はIBMで、一世を風靡した。次に小型から大型までの計算機の開発です。2番目がアップル計算機でした。3番目が Microsoftでした。コンピュータソフトがパソコンに入ると、全世界の人がそのソフトのバージョンを使うため、独占者になってしまいます。
しかし下記図をご覧ください。
- 大国アメリカは0.2%で不景気対策を実施しました。軽いデフレ作戦です。ここから米国はITという武器を使って、デフレ活動を遮断しました。
- 日本の役所はこの図のような発想を持っていませんでした。世界一に浮かれました。1995年一人当たりの所得の成長率が米国20%、日本は11%です。日本は米国以上にデフレを警戒するべきでした。
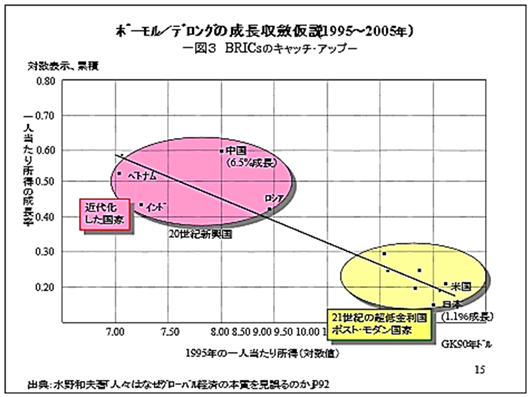
図3は1995年図を表しています。
- ①中国は成長率6.6%で→拡大政策
- ②米国の成長率は2.2%黄色→デフレ対策
- ③日本の成長率1.19%黄色→デフレ政策
- ⅰ)みなさん、上図を見てグローバリゼーションを自由な発想で世界を動かしているFRB人材がいる。
- ⅱ)中国は「米株規定額購入」+「デリバティブ方式の100倍の新株購入」で新会社の株手数料7%で購入」
- ⅲ)この方式で中国に新株を購入させた背景には、米国内に遠くない時点で、米国WASPが減少し、その時点では世界が望む製造人口を集めることが難しく、同時に米国全体として、必要な人材が、カバーできないという危惧がある。
|
| |
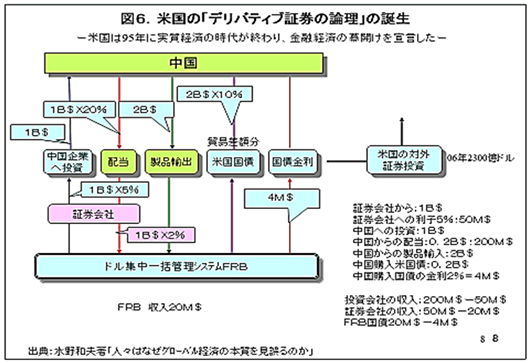
図6 将来を読み取った複雑な人材募集法 |
| |
上図は世界一の製造業を構築するために、当時世界一人口を有する中国を土台とする計画を立てることで、将来につながると感じていたトップ人材がいたに相違ない。これもユダヤ人の鋭さと、自信をもってことに当たる信念の持ち主が出現したからと考えてよい。今でもこの発想は良く飛び出せたものだと感心している。
- ①FRB (米国連邦準備理事会)日本の中央銀行に匹敵
- A. 中国本土には下部組織を動かす低居人材と、
- B. 米本土には高級部門の扱いをする部門がそだつ環境を加味したと考えられる。
- C. これだけの準備があれば、数少ない有能なユダヤ人で、
- D. 場所はどこにいても、地球上制覇は準備できたという話を聞いた。
- ②FRB人材の発想に乗って、第2の世界制覇国を練っている中国の今後を想定する必要がある。
- ③日本人はこのグローバリゼーションで何をかんがえるべきか全くわかっていない。
- ④③の答えをくださいね
- ⑤この時日本最高エリート財務省は不況対策でなく、インフレ対策を実施し、財テック投資を勧めていました。残念ながら日本国の運営は霞が関村軍団が実施の権限を握っており、世界的な経営ルールを離れても、彼らの権限を実行していることがわかりました。
- 1997年バブル崩壊から2005年査定終了まで、疑問視される方法を行ったものと感じました。あれだけ財テクでたたかれた企業が合格とは思えませんが証拠がないのは仕方ありません。
- 上記作業を終えて財務省は公共投資に使える金は200兆円用意できたと報告
- 2003年~2006年小泉政権は米国ブッシュ大統領に倣って新自由主義を採用する。
- ここでの政策は失われた10年と言われた長期不況で、需要不足が不況の原因であった。
|