|
「エンタテイメント論」(167)
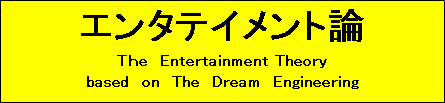
第 2 部 エンタテイメント論の本質
7 本質
●TV番組の「裏」に存在する事
筆者は民間企業の勤務時代では、音楽、エンタテイメントの「柔らかいTV番組」に出演した。岐阜県理事&新潟県参与の官僚時代では、政治、経済、社会、教育などの「固いTV番組」に出演した。経営コンサルタントの最近では、話題の新設レジャー施設に関する「ニュースTV番組」に出演している。これら多くのTV出演を通じて筆者は、一般視聴者が知らない「裏」の話を知った。この「裏」の話を本号で紹介すると前号で約束した。
しかし何故、「人生100年時代」のテーマを横に置いて、「裏」の話を先に紹介するのか? その理由は此の話が筆者を含めた多くの国民の仕事や生活に直接関係する「重大な意味」を持つからである。折角なので、此の話を知らしめた筆者のTV出演の経験をエンタテイメント論やその他の観点から論じる(後述)。
●筆者の初めてのTV出演
筆者は会社に入社2年目の23歳の時(1963年=昭和38年)、仲間達と共に日本テレビの「カラーTV実験放送番組」で初めて出演した。一般家庭には白黒テレビしかない時代である。JR有楽町駅の傍に今も昔のままに存在する「読売会館(現在 ビッグカメラ有楽町店が入居)」の「有楽町よみうりホール」で2~3カ月に1回の割合で、30~45分間の番組を結構長い期間、出演した。

出典:有楽町読売会館 & 読売ホール
wikipedia.org/wiki/AB:Yomiuri_Hall.jpg
●筆者の楽器演奏に依る社内ダンスパーティー出演と東京都内のダンスホール出演
筆者は大学を卒業と同時に富士製鐵(八幡製鐵と合併し新日本製鐵~日鐡住金~日本製鐵)に入社した。いきなり本社に配属され、社会人の第一歩を踏み出した。
直属の上司の掛長や課長には公私共に大変お世話になった。叱られた記憶より、有意義で楽しかった記憶ばかりが思い出される。なお「掛長」は誤字ではない。富士製鐵や八幡製鐵に残る「官営日本製鐵」の伝統的役職表現である。
さて本社で「ジャズバンド」が新編成され、筆者はジャズギターで加わった。当時、日本中で「社交ダンス」が大流行。その結果、本社の人事部、国内販売部、輸出部など多くの部門の幹事達は、此のジャズバンドに出演を要請した。本社ビルの大ホールで毎年何度も開催される社内ダンスパーティーに出演。多くの社員や時には役員までも社交ダンスに興じた。富士製鐵の社員への福利厚生は手厚く、社員教育も殊の外熱心であった。まさに古き良き時代であった。
出典:ジャズバンド
thumbsdreamstime.com/jazz
-band-music-women-whit
-jazz-band-concert-
151496491
人事部は毎年最初のダンスパーティーを開催。同部のダンスパーティーの幹事は筆者の友人。彼は出演料を毎年増額して決めてくれた。この出演料がその年の相場になり、他部門が従った。彼には「裏」でお礼の「一杯」に招いた。しかしこれが本稿の「裏」の話ではない。
当時、1回の出演料の総額で、5人の出演者(ピアノ、ギター、ベース、ドラム、歌手)が「豪華な夕食」をする事ができた。更に「二次会」で好きなだけ飲んでも、まだ手元に相当の額が残った。カラオケが世の中に出現する遥か昔の1962年(昭和37年)頃の話である。
またこのバンドは、社内のダンスパーティーだけでなく、仕事の隙間の夜、都内のダンスホールなどに出演してギャラを稼いだ。
●Japan as Number One
日本は世界に誇る「奇跡の復興」を遂げたと世界中から評価され、世界に誇る「高度経済成長」を達成した。筆者の給与も、賞与も、資格も、地位も上がり続けた。当時の日本の国際競争力は世界一であった。
「Japan is Number One」は世界の常識前提として、ハーバード大学教授のエズラ・ヴォーゲルは「Japan as Number One」の本を書き、世界中で大ヒットさせた。
出典:Japan as number one
amazon.com/images/Hwur0
gBwL_AC_UL amazn.co.jp/
keywords=japan+as+no.+1
同教授は日本の高度成長の原因は何か?を分析し、「アメリカ人は日本を見習え」と主張した。本の副題が「Lessons for America」となっている事で全てが分かるだろう。
しかし輝かしい、素晴らしかった日本は、今や多くの分野で世界の「蚊帳の外」に置き去りにされてしまった。現在の日本の国際競争力は、比較しても始まらない国を除くと、世界最低である。
2020年 : 世界の平均年収ランキング OECD加盟国・平均年収ランキングのトップ10ヵ国
 ■1位: アメリカ(69,392ドル)
■1位: アメリカ(69,392ドル)
■2位: アイスランド(67,488ドル)
■3位: ルクセンブルク(65,884ドル)
■4位: スイス(64,824ドル)
■5位: オランダ(58,828ドル)
■6位: デンマーク(58,430ドル)
■7位: ノルウェー(55,780ドル)
■8位: カナダ(55,342ドル)
■9位: ベルギー(54,327ドル)
■10位: ドイツ(53,745ドル)
■22位: 日本(38,515ドル)
アメリカは最低賃金が年収・時給ともに低いのに対して、平均年収となるととたんに世界1位となる。格差社会アメリカの現実が如実に表れている。日本は最低年収ランキング14位(16,989.5ドル) 最低時給ランキング14位(8.2ドル) 平均年収ランキング22位(38,515ドル) OECDに加盟している韓国に後塵を拝し、年収・時給ともにアジア諸国では最下位(OECD加盟国内)
筆者は本稿で度々述べた通り、日本は明治維新と戦時を除き、現代史上初の「構造的危機」に直面したと30年前から主張してきた。現在の日本の企業の社員の給与水準は過去30年間殆ど増えていない。構造的危機に依る当然の帰結である。
●東京都内のジャズバンドマン(歌手含む)のギャラ(報酬)の低さ
会社のサラリーマンと違ってジャズのバンドマンや歌手のギャラの所得水準は増えるどころか、以前から下がりっぱなし。筆者は現在、本職の隙間の夜、東京都内のジャズ・ライブハウスでピアノトリオ+歌手の編成でピアノを弾いて出演している。筆者はその後、ギターからピアノに転向した(コロナ危機の今は出演を中断中)。
ジャズ・ライブハウスに出演するバンドマンや歌手は、誰しもプロ意識を持ち、人前で恥ずかしくないレベルのジャズ演奏力やジャズ歌唱力の「技」を身に付けている。そして客のリクエストに応えて演奏(歌唱)する。多くの場合、出演時刻は夕方7時から11時又は12時までの4~5時間、3~4ステージを僅かな休憩時間を挟んで演奏する。時には「酔っぱらった客」の相手もする。この出演ギャラはお客の数で上下する事が多い。そのレベルは何と、コンビニで働くアルバイト料より下なのである。交通費など一切の付帯的便益はゼロ。お客が少ない時は、「一人700円」という事があった。それはコロナ危機以前の2019年11月某ライブハウスでの出演料であった。
筆者はプロ演奏家(歌手含む)を「専業プロ(演奏家)」と「兼業プロ(演奏家)」の二種類に分類して、その表現を広めている。「本職を持たない専業プロ」は、アルバイト(コンビニ勤務、修理工、建設現場の補助など)をしながら演奏活動をしている。コロナ危機などで出演できない専業プロは生活保護を受けている。
筆者の様な「本業を持つ兼業プロ」は、ギャラが低くても、出演し、演奏する機会を楽しむ。しかし何の専門技術も、何の特技も求められないアルバイトが時間給で稼ぐ金額は、演奏者や歌手の出演料の倍以上である。このギャップはたとえ「兼業プロ」でも受け入れたくない。まして専業プロでは死活問題である。儲けるのはライブハウスやピアノバーなどの経営者である。
日本ではハードやソフトの「固有技術」や「管理技術」が正しく評価されていないと云う「厳しい批判」が以前からある。しかし音楽の「固有技術」に至っては、正しく評価されないばかりか、無視されている。会社勤めの正規社員や非正規社員の給与の低さと伸び率の低さを日本の多くの学者、評論家、ジャーナリスト等が問題視する。しかしバンドマン(歌手)の給与の余りの低さと伸び率どころか減少率の高さを問題視した学者やジャーナリストなどは皆無である。
彼らは演奏家が演奏する場で飲んだり、食べたりしている。その場面で悲惨な生活と人生を送っている演奏家が実在する事に気付かない。無視している。これが日本のエンタテイメント業界の根底に横たわる現実である。もはや「業界」と云える存在ではない。筆者だけがこの問題を本稿で取り上げているだけである。
■アメリカ、ニューヨーク・マンハッタンのピアノバーでの出来事
筆者は新日鐡NY駐在員時代、事務所がマンハッタンのパークアベニューに在った。仕事帰りにマンハッタンのアチコチのバーで飲んで帰った。
ある日、某ピアノバーで立ち寄った。既に店には日本の商社マンらしき人物が数人テーブルを囲んで飲んでいた。
出典:NYタイムズ・
スクウエアー
clker.com/cliparts/
10506411times
square
彼らは酔った勢いで「日本の歌」の伴奏を黒人ピアニストにチップ片手に強要していた。彼らはその店の常連客の様であった。イタリヤ系の人の良さそうな店主は伴奏できない黒人ピアニストを庇って何度も謝っていた。しかし酔った勢いと数人の力を借りて、他の客の迷惑顔を無視し、大声で強要を繰り返した。特にその中の若い一人が下手な英語で黒人ピアニストの肩に手を掛けた。
「ムラ!」とした筆者は説得に入った。彼は、矛先を変え、筆者に釣っか掛ってきた。筆者の張り倒す動きを察知した店主は「Don’argue ! Don’t fight ! 」と筆者の手を必死に握った。
出典:決闘 alamy.com/
comp/f4tc2d/cowboy-
pistol-duel-hollywoodfort
-bravo-western-styled-
theme
此処で日本人同士喧嘩しても始まらないと思った。しかし彼は筆者を中国人と思い込み、見下した態度を示した。その事で更に頭に来た。此処で喧嘩を始めれば「西部劇の決闘」と何故か思った事を今も思い出す。筆者は腹立ちを抑える一方、店主のなだめで「決闘」にならなかった。
「ふっ!」と偶然、ピアノの上の「或る物」を見付けた。誰かがこの店に持ってきて保管させたのだろう。日本語が読めない店主やピアニストには「無用の長物」であった様だ。或る物とは、分厚い日本の「歌謡曲全集」や「ヒット曲全集」であった。それを広げると「伴奏しろ!」と強要した数曲の全てが楽譜と共に掲載されていた。「やれやれ、今夜は酔っ払いのお相手か!」と諦め、頼まれもしないのに、その内の1曲を弾き始めた。
次の瞬間、今までの喧騒が一瞬にして止み、静寂となった。筆者の弾く日本の曲のピアノの旋律だけが店中に響いた。騒いでいた連中も、店主も、黒人ピアニストも、他のお客も、「目を丸くして、ポカーンと口を開けて」筆者の顔を見つめた。今もその滑稽な顔が思い出される。まさか筆者が弾くとは! 厳つい筆者とピアノが非連結なのはアメリカでも、日本でも同じである。
「Why don’t you sing the song ? and All of you ?」と彼らに声を掛けた。我に返った彼らは、手の平を返した様に、嬉しそうに、筆者に礼まで言って、声高らかに歌い出した。
その夜は店ごと大いに盛り上がった。筆者は日本人である事を最後まで明かさず、英語で話し続け、次々とリクエストに応えてピアノを弾きまくった。ガッポリと彼らからチップを何度も何度もせしめた。チップを入れるビールの大ジョッキが現ナマで一杯になる度に、それを鷲掴みして何度も何度も黒人ピアニストの背広のポケットにねじ込んだ。
出典:ニューヨークのピアノバー
inspirationfeed.com-
content/New-York-Street-
at-Night.jpg Lower-East-Side
-Underground-Basement
-Bar-NYC.jpg&action=click
店主は筆者の帰り際、筆者の手を強く握り、イタリヤ語で謝意を何度も何度も表した。お店を救ってくれた事と黒人ピアニストへの配慮に感激した様だ。当夜の筆者の飲み代は全てタダにしてくれた。分かれ際に黒人ピアニストの目に涙が光っていた事に気付いた。店主は筆者がNYの北のスカースデールに住み、マンハッタンで働いている事を知って「是が非でも、再度店に遊びに来て欲しい」と懇願した。
以上の出来事は筆者の経験談の単なる紹介ではない。ピアノバーやライブハウスでのエンタテイメントの在り方とやり方が、店主と演奏者との関係、店主と演奏者と顧客との関係に於いて、日本(東京)とアメリカ(NY)は大きく異なっている。この事を証明する出来事なのである。従ってこの経験談は、筆者の武勇伝でも、自慢話でもない。その理由は別途説明する。
紙面の制約から、①筆者のTV出演への経緯、②TV業界などの「裏」の話、③本号の最後のNYピアノバーでの出来事について来月号以降で明らかにしたい。
なお筆者は、本稿を書いている内に様々な出来事が次々と想起されてくる。その内容をエンタテイメントの観点や経営の観点などから解説し、読者に伝えるべきではないか?と考え始める。その結果、「人生100年時代」のテーマ、エンタテイメント論の「本質論」などが後回しになる。しかし筆者としては「混乱」しているのではなく、「脱線」しているだけである。ついては今暫く、この脱線に付き合って読んで欲しい。
最後に、筆者の本稿の内容が、読者が取り組む経営、業務、PM、SEなどに役立っているか否かを評価して貰う前に、兎に角「面白い」「楽しい」と思って貰えれば、それだけで「望外の喜び」を感じる。「エンタテイメントは楽しい事が一番」なのであるから。
つづく
|

