| |
( 1 ) |
地政学とこれからの展開 |
| |
地政学には種々の地政学がありますが、20世紀までの地政学と、21世紀型の地政学は大きく変わります。まずオーソドックスな大陸系地政学と英米系海洋国家地政学の説明をし、その後は20世紀後期、21世紀型経済地政学を説明します。 |
| |
1. |
大陸系地政学
18世紀ドイツで盛んになった地政学で『国家は国力相応の資源を得るための生存権を必要する』という大陸国家系地政学を唱えた。これがナチスに大きな影響を与えた。 |
| |
2. |
英米系・海洋国家地政学
第二次大戦に勝利したアメリカは、米国海軍将校であったアルフレッド・セイヤ・マハンが『海上権力史論』で、 |
| |
① |
世界大国になるための絶対的な前提条件は海洋を把握することである。 |
| |
② |
大陸国家であることと海洋国家であることは両立しえない。 |
| |
③ |
シーパワー獲得の条件は、国家地理的位置、国土面積、人口、国民性質、統治機関の性質の5つである |
| |
|
マハンは海洋、すなわち海上交通路を制することの国益を、カルタゴ、スペイン、イギリスなどの海洋国家の歴史から学び、工業、商業の大規模化には海上交通の制覇が大きいと評価した。大陸国家は隣接国家との生存競争が存在するとの前提に立ち、故に海洋に進出するための費用を大陸国家では負担できないという考えを提示している。
|
| |
3. |
20世紀的「空の地政学」
20世紀後半は航空機の普及で地球が狭くなった。経済強国は貿易摩擦を解消するために、多国籍企業を消費地に設立し、現地人を採用して、現地の経済に貢献した。しかしこれはグローバリゼーションの前触れといえた。
|
| |
4. |
21世紀型の新経済地政学『電子・空間活用型地政学』
これは20世紀の地政学と全く次元の異なる地政学で、3つの空間領域に分類した。 |
| |
4.1 |
電子・金融空間型地政学 |
| |
① |
陸の地政学的ビジネス戦略 |
| |
|
・ |
ローマ帝国時代の地政学(全ての道はローマに繋がる) |
| |
|
・ |
シルクロード時代のビジネスはシルクロード上の各国が通行税を取ることでキャラバンを保護したことで成立していた。 |
| |
② |
海の地政学的ビジネス戦略 |
| |
|
・ |
大航海時代となり、最初に制海権を握ったスペインは航海の危険はあったが、南米大陸での金の発掘で巨額の利益を得て、海のリスクを吸収し巨万の利益をあげた。 |
| |
|
・ |
オランダはシルクロード経由の東洋の宝物貿易を海路でおこなった。海路による貿易はシルクロードによる運搬量より巨大化され、安価で運搬できるため巨額の収益をあげた。しかしこの時代の航路は喜望峰経由の危険なもので、そのリスク分担として株式会社方式が採用された。オランダは東インド株式会社を設立し、航海ごとに株を発行し、リスクを株主が分担し、継続的にビジネスの発展につとめた。オランダは欧州の王侯、貴族が欲しがる日本の陶器を長崎で買い求め、巨利を得た。 |
| |
|
・ |
その後スペインの無敵艦隊を打破したイギリスが制海権を握り、イギリスによる東インド会社を設立し、インドにおける綿花貿易で経済的な覇者となった。 |
| |
|
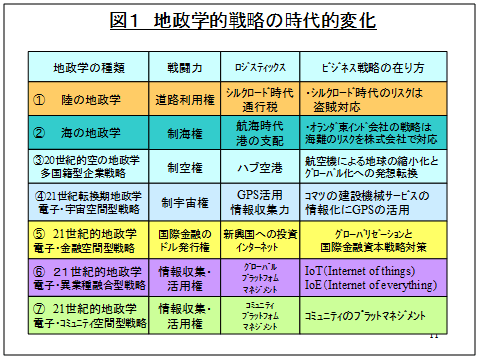 |
| |
③ |
20世紀的空の地政学 多国籍型企業戦略
第二次世界大戦で日本軍の真珠湾攻撃が空の戦闘機、爆撃機と海中からの潜水艦攻撃で、制海権時代の戦略を覆した。日本は初期の戦略の成功にかかわらず、海軍正統派は巨艦戦略を固執したため、真珠湾での制空権の重要性を認識した米国海軍にミッドウエイ海戦で敗れた。第二次大戦中の米国は空軍のバックアップで強化した海軍力で連合国を勝利に導いた。米国の真の勝利は連合国側への兵器の販売であった。第一次大戦後の覇者イギリスは、第二次対戦でドイツと戦いで多くの富を消費し、反対に米国は世界中の富の半分を支配することに成功し、世界の覇者となった。
日本は第二次大戦後朝鮮動乱が起こり、米国の対ソ連への戦略上の観点から、日本を防衛上の味方にする方針となり、朝鮮動乱によるビジネスで日本経済を立て直す資金を獲得し、経済力を復興することができた。海洋国である日本は、制海権を握る米国の傘下で、海を活用する貿易で日本製造業を活発化し、1990年には製造業世界一となった。しかし1990年を境に経済は停滞する。これ以降は1991年のソ連崩壊で国際金融資本の帝国主義化が顕著になり、日本の製造業は更に勢いを失った。 |
| |
④ |
21世紀転換期地政学宇宙空間型戦略 (1990年~2000年)
ソ連崩壊後の世界で21世紀型ビジネスの芽が育ちはじめた。 |
| |
|
a. |
国際金融資本の世界制覇への動きが芽生えた |
| |
|
b. |
インターネットの普及が1995年を目処に世界中に拡大した。 |
| |
|
c. |
資本主義国の企業経営のデジタル化による経営のスピード化への動きが、この時期から、21世紀初期にかけデジタル化が米国内で普及し、米国の企業の経営に変化へのスピードが増した。 |
| |
⑤ |
21世紀的地政学 電子・金融空間型戦略
国際金融資本のグローバリゼーションへの動き |
| |
|
a. |
先進国の経済成長率低下により、国際金融資本は新興国へ本格的に投資を開始 |
| |
|
b. |
成長率の高い新興国諸国への資本投資の手法として、米国内投資者には掛け金の100倍のレバレッジのドル融資付きデリバティブ証券を発行 |
| |
|
c. |
新興国特に中国、台湾へのMES (大量生産型製造設備の導入) による、低価格製品の製造を可能にする政策 |
| |
|
d. |
中国、台湾、韓国への投資は株式の50%以上を持つ外資としての権利確保。投資回収のため、米国の製造業を消費地に移転した形として米国内での製造をとりやめ、製品購入に切り替え、外資企業が成り立つ手法を採用。この方式で米国は中国に対し、赤字貿易となり、黒字国が米国国債を大量に購入し、中国は世界最大の米国債保有こくとなった。 |
| |
|
e. |
国民の1%の富豪に、50%の富が集中している。 |