|
リスクマネジメントの最新動向 Advanced PMR Club 幹事 坂井 剛太郎(サカイ ゴウタロウ) [プロフィール] :7月号
1. はじめに プロジェクトマネジメントの世界では、リスクマネジメントはその構成要素のひとつにすぎず、「直面するリスクを特定し、管理するためのマネジメント」と定義されている。 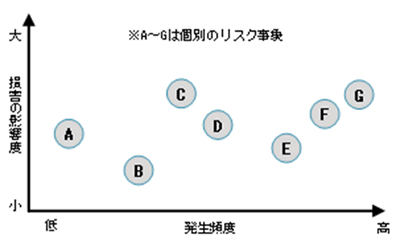 図1. リスクマップ 「リスク」は、問題点として顕在化する「可能性」(発生頻度)と顕在化したときの「影響度」という要素で特定される抽象的な概念(図1.)であるため、リスクの特定プロセス(リスクアセスメント)では、問題を起こしやすくする環境(ハザード)や問題を顕在化させる行為(ペリル)・きっかけ(トリガー)、影響度が具体的に発生する対象物(エクスポージャー)を起点として特定して、リスクマップ上に定義していくことになる。 一例をあげれば、床に落ちたバナナの皮(ハザード)を、スマホを見ながら急いで歩いていた(ペリル)ために、踏みつけてしまい(トリガー)、転倒(リスクの顕在化)した。その際の影響度は、怪我(身体)・汚れ(衣服)・損傷(腕時計・スマホなどの装身具)・機会損失(スマホ損傷による情報遮断)などが考えられるのである。(図2.)影響度は、損害額の仮想算出により評価することになる。 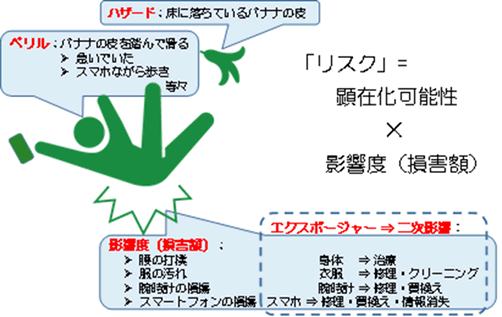 図2. リスクの基本的構成要素 特定されたリスクの管理プロセス(リスクマネジメント)は、リスクコントロールプランとリスクファイナンスに分類できる。リスクコントロールプランでは、回避(契約形態・条項による除外や辞退・撤退等)、軽減(事前の対応策立案による実行管理体制強化等)、分散(対応リスクの専門性を持つメンバーとのコンソーシアムの結成等)、移転(ステークホルダーへの転嫁等)の手法があり、リスクファイナンスでは、移転(民間・政府保険による対処等)、保有(リスクマネーの事前計上またはキャプティブと言われる自家保険による負担等)の手法がある。リスクマネーには、エスカレーション(価格上昇想定対応)、アローワンス(発生対象は確定しているが仕様規模が不明なものへの対応)、コンティンジェンシー(発生対象事態が想定できない不確定要素への対応)が定義されている。 2. 「リスクアペタイト」と「リスクトレランス」 これまでのリスクマネジメントでは、リスクの顕在化による影響は損失・損害を中心にしたものとなっていたが、近年「機会損失」をリスクと捉えるようになり、想定利益の取得を影響度と考える考え方が定着してきている。現状から機会を模索する指向性を「リスクアペタイト」と言い、金融庁により有価証券報告書への記載が求められるに至っている。同時に未知の機会への挑戦には大きなリスクが伴うことから、自らの体力(「リスクキャパシティ」)を考慮した上で挑戦からの撤退を決断する限界点を事前に設定する必要があり、この限界域を「リスクトレランス」という。この時、機会によって得られた益を「リワード」、負の影響度が「リスクキャパシティ」を超える状態のリスクを「フェイタルリスク」と新たに定義されている。 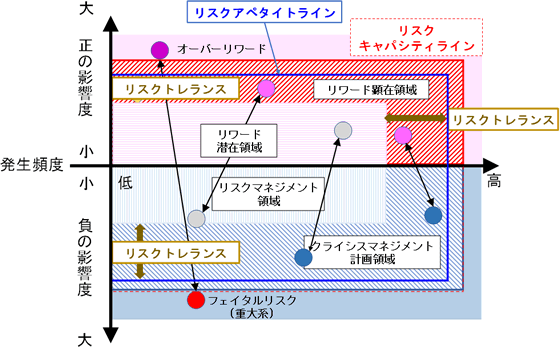 図3. 「リスクアペタイト」を反映したリスクマップ 3. 企業環境の変化 2019年12月に中華人民共和国湖北省武漢市で初めて確認された新型コロナウイルス(COVID-19)は、2020年に世界的なパンデミックとなり、今日に至るまで世界的な活動の停滞を引き起こしている。 また2022年2月に始まったロシアによるウクライナ侵攻の影響は、世界的なエネルギー危機や食糧危機に及んでいる。 さらに近年の企業の社会環境は確実に変化している。 1-1)働き方改革 COVID-19感染拡大防止対策として在宅勤務が拡大する中、パソコンやタブレットをはじめとした電子機器の社員への配付や通信環境の整備等が急激に推進され、それまで対面業務を当たり前としてきた働き方が大きく変化した。 またリモート勤務が可能な職種においては、事務所コストの削減という雇用主側ニーズと、通勤時間削減と住環境改善という雇用者側ニーズが合致し、郊外或いは近隣県等への移住といった動きも活発になった。 1-2)デジタル・トランスフォーメーション(DX)と人工知能(AI) 前項の働き方改革に伴うリモート勤務に係るDX化推進に伴い、経費処理や教育などの社内DX化も推進されることになった。 またコールセンターなどでは、出勤者の不足を補うAI化の推進が図られるなど、人流の変化に伴うサービスのDX化・AI化が多角的に多様的に推進されている。 1-3)円安 エネルギーや食糧を輸入に頼る日本にとって、ロシアによるウクライナ侵攻は大きな負の影響をもたらすことになった。各国の政策の差異の歪みにより円安が急激に進むと共に、国内外での格差が拡大した。 格差課題を抱える企業や個人は、DX化等による新たな自己改革や国外に活動の場を求める方向性を取るが、一旦変化に追従して変化した企業や個人は元の活動様式に戻ることはできず、新たな生活様式に変化している。 また、日本特有の長期的課題として挙げられるのは少子高齢化であろう。これに終身雇用制度の崩壊や円安による国際間格差が拍車をかけ、さらにCOVID-19やウクライナ侵攻が企業環境の急激な変化を加速させている。 2-1)人的資源の流出 円安や国際間格差を逆手に取り、海外企業によるヘッドハンティングや、個人自ら移住するケースが増えている。この傾向は、特に役職定年や定年再雇用を迎えたシニア層や、就職後に不満を抱える若年層に多く見られる。 ここでは、シニア層の持つ技術やノウハウの流出が二次的に起こっていること、技術やノウハウの引継ぎを受け手である若年層が少子化と海外流出で減少しており、長期的に日本の国力低下につながることは間違いない。 2-2)資源のサブスクリプション化 VUCAといわれる変化が速い時代において、市場のニーズが刻々と変化することが考えられる。商品・サービスもそのニーズに追従せざるを得ず、モノを資本として保有することが大きなリスクとなる。保有の代替手段として考えられるのがサブスクリプションである。 個人が車の購入・保有ではなくリースやレンタルを活用することや、企業での備品のリース化拡大やアウトソーシング化などは、広義のサブスクリプションと考えることができるが、経費効率の面だけでなく、取捨選択については事前に十分検討すべきであると考える。 2-3)投融資条件の厳格化 投融資を受けるにあたっては、事業形態によって手順を考える必要がある。起業などのケースはともかく、海外の機関投資家を含めた投融資の獲得を目指すのであれば、SDGsの背景にあるESG経営体制や改訂コーポレートガバナンスコードに明記されているリスクアペタイトについての記載の意味を十分に理解し、体制・しくみを整える必要がある。 4. 企業価値の変化 M.フリードマンによる「企業の社会的責任は、株主利益の最大化である」とした利潤追求の目的が長らく資本主義の原則とされてきたが、近年は地球規模の問題とされる社会格差や自然資本の解決が重視され、現在の事業活動の負債を次世代に送ることなく解決すべきというサステナビリティ主義にシフトしている。(図4.) 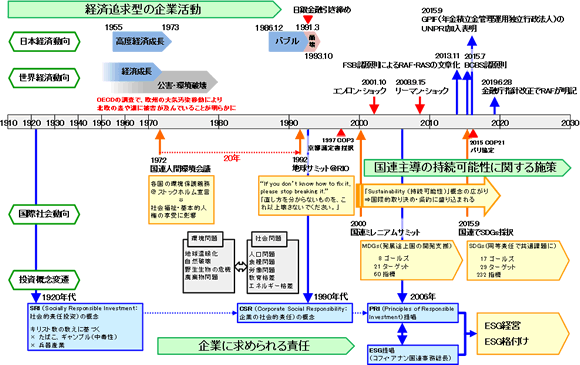 図4. 企業を取り巻く環境の変化 このような動向は国連が主導しているのだが、2000年の国連ミレニアムサミットで採択されたMDGsは先進国による発展途上国の開発支援という目的であったが双方からの協力が得られず、2015年に新たに先進国も発展途上国も同等責任とした共通課題としたSDGsを採択した。このSDGsのターゲットは経済活動を担う企業に向けたものとなり、目標を与えるだけでなく、経営面での縛りとしてESGが同時に採択されている。 SDGsには17のゴールがあるが、これらを構造化したストックホルム大学のウェディングケーキモデル(図5.)を見ると、SDGsとESGの関係性が良くわかる。 経済圏と社会圏(Society)にまたがる活動を展開する企業に対して、社会圏を支える生物圏(Environment)にも責任を持たせるとともに、これら三つの圏に対する一貫した姿勢をリーダーシップ(Governance)で串刺しにするという構造なのである。 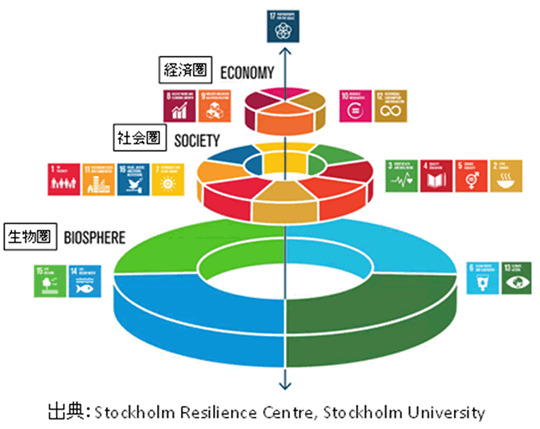 図5. ウェディングケーキモデル 2019年には米国の経営者団体ビジネスラウンドテーブルが株主至上主義を見直し、企業が説明責任を負う相手は顧客、従業員、サプライヤー、コミュニティ、株主の5者とした。そのコミュニティには、サステナビリティ活動の対象である地球環境が含まれている。 国際統合報告フレームワークで示されたオクトパスモデル(図6.)では、従来のバランスシート(貸借対照表)に示される財務資本(カネ)や製造資本(モノ)の他に、経営資源に含まれる人的資源(ヒト)や経営産業省が示す新たな経営資源としての知的資本(チエ)、さらには社会・関係資本、自然資本が含まれており、企業活動のインプットとアウトプットの双方に位置付けられ、企業活動のビジネスモデルとの関係性が示されている。 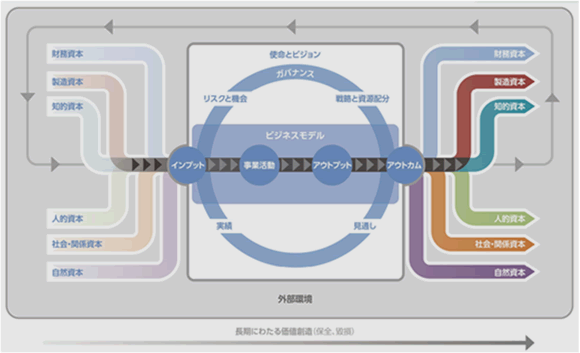 出典:国際統合報告フレームワーク 図6. オクトパスモデル 企業活動への影響としては、地球社会の一員としての存在意義を明確にする「パーパス経営」へのシフトと共に、これまで顕在化しない限りその補償や対策を求められることは無かった社会資本や自然資本の負債への対応の常態化が考えられる。コーヒー豆や綿花のサプライチェーンにおける労働力の搾取問題や森林伐採による洪水発生などの自然破壊問題などは、その事例としてよく知られている。 売上高が同じで、社会資本や自然資本への負債対策を盛り込むとすれば、利業利益は現状以下になること(図7.)は必然であり、企業活動の維持のための改革が必要となる。 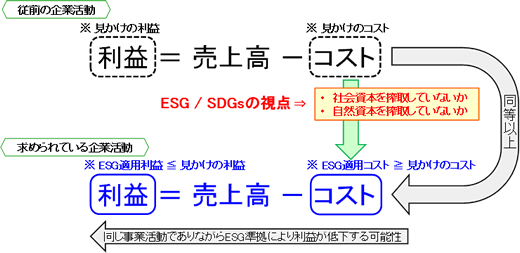 図7. 「真のコスト」の影響 短期的には現事業領域内での受注拡大とコスト削減で対応することになるが、中長期的には事業領域の拡大を検討する必要がある。現事業領域の隣接市場や商品・サービスの用途展開・仕様変革から新規事業開発まで事業拡大には多段階のレベルがあるが、従来のリスクマネジメントの適用対象は現状の市場や商品・サービスからの変化の少ない領域に限られ、新規事業開発など変化の大きい領域への挑戦には「リスクアペタイト」の適用が必要不可欠なのである。同時に新規事業開発など変化の大きい領域への挑戦には大きなリスクが伴うことから、自らの体力の限界域を考慮した「リスクトレランス」を事前に設定する必要があることは言うまでもない。(図8.) 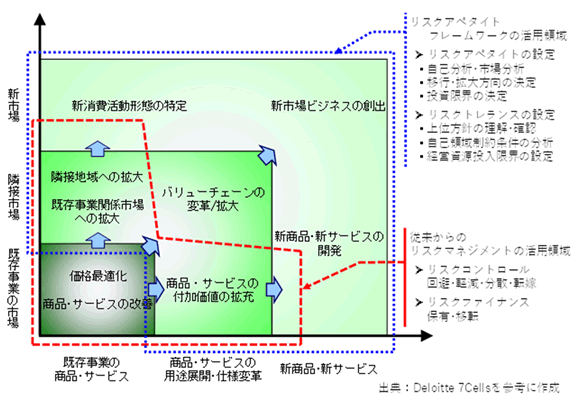 図8. 企業存続のための中長期施策 5. おわりに この数年、社会の大きな変化の中にいることを実感しているが、特に会社人生で過ごしてきた会社と個人が一体化してきた環境自体が変わってきていると考える。 その中でリスクをマネジメントするためには、会社としての判断基準の確立と、個人のリスクセンスの醸成が不可欠であると考える。会社の判断基準は企業文化や方針であるが、前述の通り、社会の一員としての存在意義を示したパーパス化は必至である。 個人のリスクセンスについては、リスクに対する視点の拡大が必須であり、自分の立ち位置やリスクの顕在化により影響を受けるエクスポージャー、時系列的要素などを層別して考えることが必要である。経験による気付きの広がりはもちろん、以前異業種メンバーでの研究会で創作したリスク特定キュービックモデルのようなツールを活用して、意識的に視点を広げてリスクの洗い出しをしていくことも必要である。(図9.) 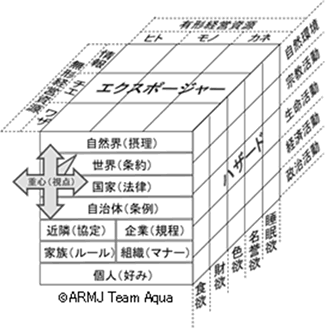 図9. リスク特定キュービックモデル 私とリスクマネジメントの関係は、タイ・アメリカでの7年の海外駐在を通じて異文化対応リスクを体験し、その必要性からPM資格に先んじて修得したことに始まる。それ故、リスクマネジメントはプロジェクトマネジメントの構成要素のひとつではあるが、独立したマネジメントシステムでもあるため、どちらかを優先することなく両者を対等に扱っている。 プロジェクトマネジメントのプロセスにおいてリスクマネジメントを実行するだけでなく、リスクマネジメントの特定プロセス・管理プロセスにおいてP2Mを導入し活用しているのである。さらに本稿で取り上げた「リスクアペタイト/リスクトレランス」の導入時にもP2M手法の活用が有効であることは実証済みである。(図10.) 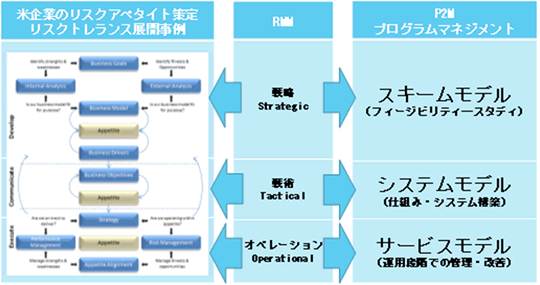 図10. リスクアペタイト策定プロセスとP2Mの融合 [参考文献]
|