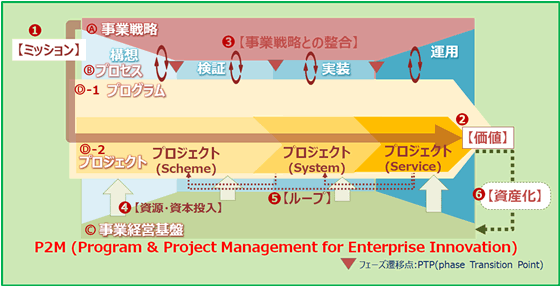見えてきたP2Mの普及・推進の課題と2025年度の活動計画
P2M普及・推進部会 藤澤 正則(PMR) : 4月号
- 1.はじめに
P2M普及・推進部会は、2023年4月から活動を開始して、丸2年が経過しました。
昨年の9月には、P2M標準ガイドブック改訂第4版が発売され、活動もそれに合わせて、大きく変化してきました。そこで、これまでの振り返りと2025年度に進めていくことをまとめました。
- 2.活動目的
「P2Mの基本的概念の普及促進のため以下の活動を行う」
- ① プログラムマネジメントの重要性の普及・促進
- ② P2Mの概念を広く一般に普及・促進するための教育・宣伝活動
- ③ PMAJのホームページなどを通してP2Mの情報提供
- ④ P2Mをカリキュラムとして取り入れている研究機関との連携
- ⑤ P2M紹介資料の作成や関連図書の出版
- ⑥ P2Mに関する研究会の主催など
- 3.2024年度のP2M普及活動の取り組みの検討と実施事項
- ① PMAJホームページへの掲載:P2Mの栞での情報提供
- ② P2M標準ガイドブック改訂第4版の販売状況の把握
- ③ 執筆者へ利活用依頼:大学などでの活用
- ④ P2M標準ガイドブック改訂第4版の理解度向上:SIGの立上げあり
- ⑤ 会員向けセミナーの実施:セミナーやシンポジウムを通じて、情報提供
- ⑥ 会員向けのジャーナルやオンラインジャーナルへの投稿:情報提供
- ⑦ 関連団体へのアプローチ:IPA、JUAS、デジタル庁、国際P2M学会など
- ⑧ 会員向けの特典販売の調査:調査結果、難しいと判断
- ⑨ 法人会員向けの取り組み:P2Mの説明や資料の提供を実施
- ⑩ メディアへの取り組み:日経コンピューターなどへの掲載
- 4.価値を提供する空間(場)と人、情報から見えてきたことと課題
- ① P2Mを活用するための情報について
- ・ 実践する知識体系としては、充実してきているが、理解するのが難しい
- ・ 業務スキルからのアプローチだけではなく、基礎知識としてのP2Mの提案が必要
- ・ 業種や階層にあった情報を提供する資料が少ない
⇒わかりやすい資料が必要
- ② P2Mを活用する対象者から見えてきた課題
- ・ エキスパートモデルはあるが、エントリーモデルやミドルモデルが必要
- ・ 実務でプロジェクトに関わる人には、プログラムの必要性が伝わっていない
⇒対象者に合わせた情報の提供
- ③ 関連組織やPMAJ内の情報提供みたからP2Mを普及するための課題
- ・ 関連する組織や会員向けの実施した結果、認知度は低い
- ・ まだ、活用事例が少ない、または、活用しにくい
- ・ 特に主要な会員の所属するIT業界では、プロジェクトマネジメントが中心で、プログラムマネジメントの要請は少ない
⇒個人会員、法人会員、関連する組織に合わせた資料の作成が必要
- ④ P2M資格取得と取得後のフォローアップ体制の課題
- ・ P2Mを理解するステップとして、資格認定制度はあるが、取得する価値や知識取得後実践するための機能や情報提供が必ずしも充実していない
⇒資料の作成と情報提供する場の構築が必要
- 5.2025年度の活動コンセプト
- ・ これまでは、会員の皆様と、関心や興味を持って頂いた人や関連する組織を中心に進めてきましたが、会員の属する企業の業種業態、世代交代による価値基準の変化の中で、これまでの範囲の人に加え、より多くに人が興味や関心を持っていただき、知識として習得したいと考えるP2Mになるように下記のことを考えています。
- (1) P2Mを「わかりやすく・使いやすく・成果につながる」モデルにしよう!
- ・ 興味を持っていただくために、きっかけとなる場とわかりやすい資料の作成
- ・ 活用方法は「ないと困る・あると便利・どちらでもない」の「あると便利」を実現
- ・ 組織への提案資料として、活用事例とともに活用している人の紹介の行う
- (2)資料の検討案
(例)オーケストラの演奏会の企画、実行、運用(開催)はプログラムである
- ・ 自分たちの締め切りのある想いを実現していくには「つなぐ・変える・続ける」が基盤
- ・ P2M事業モデルを活用して整理してみる
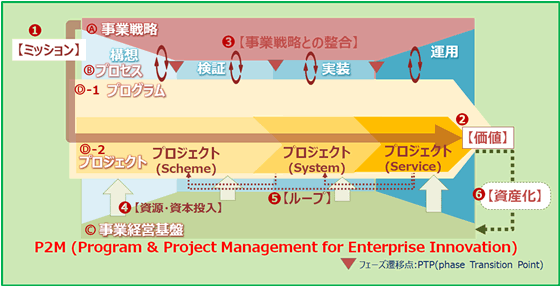
図 1 P2M事業モデル
【構成フレーム】
- (A) 事業戦略「お客様に音楽を通じて、共に喜びを分かち合いたい」
- (B) プロセス「自分達は演奏を楽しみながら、お客様には喜ばれたい」を実現する
- (C) 事業基盤「メンバー同士の相互研鑽により、一人ひとりが成長できる」
- (D) プログラム・プロジェクト「前提条件や価値基準が変化する中で、効率性と有効性のある試行錯誤を行い、締め切りのある自分達の想いを実現する」
| スキーム |
「想定するお客様に合った企画案の作成」と関わる人への説明と合意 」 |
| システム |
「個別の演奏者の準備と指揮者を含めた曲全体の調和の準備」
「演奏会全体の構成の準備」
「開催に向けた会場と受け入れ体制に関する準備」 |
| サービス |
「指揮者、演奏者、関係者がまとまり、音楽を提供して、時間と空間を
共有したお客様が感動し、喜ばれ、感謝される」 |
【事業モデルとP2Mの3Sモデルの関係性】
- ① ミッション「お客様に音楽を通じて、共に喜びを分かち合いたい」と考えている人の集まり
- ② 価値「自分達は演奏を楽しみながら、お客様には喜ばれる」
- ③ 戦略との整合性「この経験を通じて、関わった人は、実感し、次につなげていく」
- ④ 資源・資本の投入 「スパイラルアップによるレベルアップと内容に合わせた実践でのレベル向上」
- ⑤ ループ「やってみたい・一緒にやってみたい・やってみた・やってよかった・またやってみたいとまた演奏会に行きたい」
- ⑥ 資源化「新しいメンバーやコンサートを見に来ていただける人への情報提供と活用」
- (3) 実際に活用されている人の紹介
- ・ 実際に活用されている人のヒアリングと事例紹介をまとめる
- (4) 情報の開示方法
- ・ 9月に開催されるPMシンポジウムのブースの展示を行う。
- 6.参加するメンバーの募集
この部会では、一緒に感じて自ら考え行動する人材を募集しています。
活動するメリット:実際に実践している人の行っている情報を知ることができます。
活動方法:月1回のMTG(遠隔:1時間程度)
- ・ お問い合わせ先 代表: 藤澤 正則 メールアドレスは
 こちら こちら
以上
|