|
PMリーダー/マネージャーにおけるキャリアの転換 キャリアコンサルタント PMR 森 邦夫 : 4月号
筆者は定年退職後、IT系社員の転職支援や学生の就職支援を行いながら、P2Mの普及と育成の可能性を探ってきた。しかし、その難しさを痛感し、2月の「P2Mクラブ」で報告を行った。現場を離れて6年が経過しているため、課題認識を共有する目的で、事前アンケート「PL・PMにおけるキャリアの転換 - 現状分析」を実施した。本稿は、その結果と「P2Mクラブ」での発表をまとめ、導いた仮説を報告するものである。 【PMキャリアマップ】 中小規模IT系企業の現場での【PMキャリアマップ】を示す。 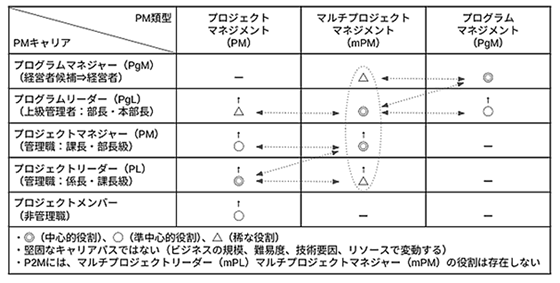 【導かれた仮説】 1.マルチプロジェクトマネジメントの課題と現実 P2Mでは触れられていない機能で、マルチプロジェクト(複数プロジェクト)マネジメントを行うリーダー(mPL)とマネージャー(mPM)が存在する。特に、多品種少量型の受注開発では、この役割を、PL・PM・PgL・PgMが担っている。 マルチプロジェクトでは、プロジェクト群は個々に独立しており、プログラムのように統合された概念を求められるわけではない。またプログラムマネジメントの実際は、企業のミッションや価値創造よりも、経営者の指示による売上・利益の追求が優先される。その結果、プロジェクト単位で収益を確保する必要性が生じ、実態としては、マルチプロジェクトに近い運営になる。筆者の経験では、プログラムマネジメントは工数管理と調整が大きな負担となり、最終的に各プロジェクトの納期遵守が最大の課題となっていた。 2.P2M普及の鍵は経営者との連携と実績の共有 P2Mの成功体験を持つPgL・PgMが経営者となり、その活用を広めることが普及の鍵となる。しかし、経営陣の83%がP2Mに関心を持っておらず、普及は容易ではない。そこで、PMRなどの資格者が経営陣と連携し、自社でP2Mを実践して、成果を示すことが重要である。このプロセスを経験した人材が将来的に経営者となることで、P2Mの普及が進むと期待される。 3.mPL・mPMから経営視点を持つPgL・PgMへの転換の難しさ mPL・mPM(マルチプロジェクトリーダー・マネージャー)が経営者候補として成長し、最終的に経営者へとキャリアアップする際には、売上・利益の追求だけにとらわれない意識改革が求められる。経営者にとって、売上や利益はミッション達成の手段にすぎず、単年度の損益計算書(P/L)の向上だけでなく、中長期的な貸借対照表(B/S)の健全化を重視する必要がある。しかし、mPL・mPMにとって貸借対照表は馴染みの薄い指標であり、この視点を持つことが大きな課題となる。経営者は「将来の貸借対照表(A)」と「現在の貸借対照表(B)」の差分(A-B)を埋めるための損益計算書を考える。この差分を埋める手法として、プログラムマネジメントが非常に有効であると考えられる。 4.ベテランSEのPDCA課題とAI時代のアジャイル管理の難しさ ベテランSEの多くは、マネジメントに苦手意識を持っている。その対策として、業務をPDCAサイクルに当てはめ、問題点を検証(C)是正(A)した上で次のサイクルへ展開する作業を通じて、「マネジメントは役立つ」と認識できれば、P2Mを学ぶ動機につながる。その際、PMBOKにあるように、初学者向けの方法論を説いた書籍もあるとよい。一方、筆者が注目するのは、相互に連携するAI機能を備えたアジャイル開発群を理解することの難しさである。開発の一部が不調になると、連鎖的に他のプロジェクトに影響が及び、そこにAI機能も加わるため、因果関係を踏まえた現状分析・判断が難しくなる。このような環境では、従来のマネジメント手法だけでは対応が困難となる可能性がある。 5.中小企業のためのベンダーマネジメント強化の必要性 現在のプロジェクトマネジメント手法(P2MやPMBOK)は、大手企業(プライム企業)を前提としており、中小企業には適用しにくい。特に小規模企業は厳しいQCD(品質・コスト・納期)を求められ、「ビジネスパートナー」ではなく「下請け」として扱われがちである。本来、他社との連携は対等なパートナーシップに基づくべきである。そのため、P2Mが「ベンダーマネジメント機能」を強化し、中小企業との共存を前提とした仕組みを整えれば、より幅広く活用され、中小企業の成長にも貢献できるだろう。 6.P2Mの活用は成功事例の後追いではなく実践から 成功したビジネスをP2Mで解説することには意義があるが、第三者が「後付け」で分析するやり方では限界がある。理想的なのは、PgLやPgMが初期段階から、P2Mを活用した実践事例を示すことで、後進が標準ガイドブックと照らし合わせながら検証し、自分なりのプログラムマネジメント手法を探求できる環境を整えることだ。 7.現場の負担を減らすマネジメントの工夫 開発現場では、短納期やコンプライアンス対応、設計開発支援ツールなどの負荷がある中で、さらにP2Mを導入すると、現場の負担が増え、作業時間を圧迫する懸念がある。特にマルチプロジェクト環境では、リソースが分散し、メンバーの一体感が欠け、統一的な管理が難しくなる。この結果、スキル向上やキャリア形成の意識が低下し、成長が停滞するリスクが高まる。さらに、業務負荷が高い企業では、後進育成の時間が確保できず、上司の個別指導や個人の自己研鑽に頼るしかないのが現状である。これらの課題に対応するためには、簡単で分かりやすい「中小企業向けP2Mガイドブック」の整備など、負担を軽減する工夫が必要である。 【総括】 今回の調査によると、PM経験者の82%が「PMの経験は次のキャリアに役立つ」と考えている一方、実際に具体的なキャリアプランを描けているのは46%にとどまっている。また、P2Mの活用については、導入を推進するリーダー不在やリソース不足が課題とされている。さらに、P2Mの知識がプロジェクトの成果向上に貢献すると認識している人は72%であるが、実際にP2Mをプロジェクトで活用し、成果を確認したのは17%にとどまっている。 これらの課題を解決するには、PL・PMの育成を強化する施策が不可欠である。具体的には、チーム型OJTの導入や、上司の指導力向上が求められる。また、企業内で経験豊富なPL・PMがメンターとなり、若手を指導する仕組みを整えることが成長を促す機会となる。さらに、P2Mの導入を支援するコンサルタントの育成と連携も重要な取り組みとなる。企業内外でP2Mの専門家を増やし、実務による成功事例を積み重ねることで、より多くのPL・PMがP2Mを効果的に活用できるようになると考える。 最後に、PL・PM((プロジェクトリーダー・マネージャー)のキャリア転換を支援するためには、図に示したマップと「経営者育成プログラム」の連携が重要だと考える。 PL・PMは、単にプロジェクトの統括にとどまらず、企業全体のビジョンを理解し、経営視点を持って経営と現場をつなぐ役割を担う。企業は各事業に適した現実的なキャリアパスを明確にし、それを運用することで、PL・PMが円滑にPgL・PgM((プログラムリーダー・マネージャー)に進む道を開くことができる。この仕組みを試行錯誤しながら構築することが、成功への道だと考える。 以上
|